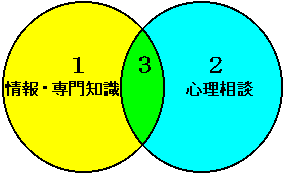
相談というのは二種類あります。極端に言えば、まるっきり性格の違った相談があるんです。
平成アーカイブス <研修会の記録>
以前 他サイトに掲載していた内容です
|
9月27日勉強会2 [講師:西光義敞先生]
![]() : カウンセリングの勉強をする前に、ちょっと黒板を使わせていただきます。
: カウンセリングの勉強をする前に、ちょっと黒板を使わせていただきます。
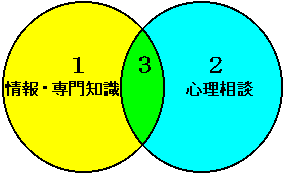
相談というのは二種類あります。極端に言えば、まるっきり性格の違った相談があるんです。
一つは、『情報・専門知識』です。自分は専門的な知識も情報も何も無い、と。だからその専門知識や情報をもっている人に相談に行く、という場合です。「法律相談」というのはてき面にそうですね。色々法律にからむ、例えば日照権問題とか、遺産の相続だとか、離婚問題とか。離婚問題は心の悩み相談でありながら法律がからんでいます。
福祉の場合でも、例えば、家に障害児を抱えているとか、お年よりが居る、こういったことをどうしたら良いのか。老人ホームに頼んだらいいのか、在宅でも何かサービスしてくれるのか、どこにどういう書類があって、どういうふうに使ったらいいのか分からない訳でしょ。だからこの相談に応える人は、やはり福祉六法的なことはよく知っておって、社会福祉に関する専門知識、情報を持っておらんと、こうした相談には応えられないわけです。「行政相談」でも、「法律相談」でも全部そうですね。
そうすると、先ほど仰ったようなことは、やはり宗教に関する知識ですから、一般の人は持っておらんわけです。世間常識に従って「先祖供養してください」と、こう言うておるんですよね。けれども、僧侶としての真宗の専門の立場から言ったらおかしいんで、真宗はそういうことは言わんわけですから、そのへんはちゃんと知ってほしい訳ですね。そうすると、こちら側(1:情報・専門知識)になるわけです。
もう一つは、それこそこれ、『心理相談』なんです。別にお金が無くて悩んでいるわけでもない。法律知識を知りたいと思っているわけでもない。悩みがどこでどう起こってきているのかも分からない。
例えば登校拒否。頭で考えたら義務教育の段階では学校行ったらいいことぐらい本人も分かってます。そやけれども、学校へ行けないんでしょ、あれは。初めの頃は「登校拒否」と言っておったんですが、拒否というのは「俺は学校行かん」と自由意志で「行かない」というのが拒否でしょ。でも学校行かない子は「行けない」んですよ。頭では行きたいと思っているし、周りの者も「行け行け」言うし、自分も行きたいのに、朝、目が覚めたら、行けないんです。難儀ですよね。
また、拒食症・過食症。がばがば食べるかと思ったら、ある日突然、ぱっと何も食べないという人が段々増えてますね。「これは明らかに医療問題だ」というんでお医者さんで看てもらうと、別に何もない。医者の立場から言うと「思い当たる原因はありません」と言われる。
だから、お医者さんという専門知識でどうのこうのするということでは解決はつかない訳です。
この領域(2:心理相談)の悩みが多様化・深刻化していってます。だからそういう人たちに「ああしなさい、こうしなさい」と言ってみても、ほとんど役には立たない。この二つが絡んでいるんで、両方とも対応を変えなくてはいけない。だから相談員になるといっても、こちらの相談(1:情報・専門知識)が中心なのか、こっち(2:心理相談)のことなのか。それでこっち(1)の代表的なものは法律相談でしょうね。
お坊さんが相談を受けて、「真宗ではこういうことはしません」とか、「納骨はいつするんや」とか、「仏壇のお飾りはどうや」とか、「真宗と禅宗の違いはどうや」とか、こういうことを知りたいと思って相談しに来たら、こういう(1)知識をきちっと持ってないと、専門職としてのお坊さんではありません。だからしょっちゅう教学や宗門法規を勉強せんなんわけです。だから、先の質問はこの問題(1)がからんでいる。その立場で言うと「困る」と、こうなる訳ですね。
そういう意味の相談に乗るのか、そうじゃなくてこちらの心理問題ですね、こちらのところ(2)の悩み。自殺を考えているような人には、何か事情がからんでいたのかも知れないけれど、やはり心理問題でしょうね。自殺は自分で思い悩んで、追いつめていって、自分で命を絶つわけです。自殺願望。<死にたい>と思って生きている人は沢山います。だからそんな時には、こんな(1)勉強してもあかん、こっち(2)の勉強しないと。それを担当するのがカウンセラー、セラピスト、精神科医です。
だから、こちらの立場(1)か、あちらの立場(2)か二種類ある、ということを知ってもらって、相談者、相談員になるといっても、仕事としては種類が違うんだ、と。こちら(1)の専門家になるんだったら、専門の知識を持っていないといけない、こちら(2)の方は、必ずしもそうではない。極端に言ったら、面接するけれども――
「・・・」
「ここでの相談は、どこにも出しませんので、辛いことがあったら、何でも仰って下さい」
「・・・」
と、こうして、3分・5分・10分・30分・1時間過ぎて、何も言わずに終った、ということも私は何度も遇っていますね。

ですから、さしあたってカウンセリングは、こちら(2:心理相談)の勉強だということです。
教団の法式規範やお勤めの仕方を知って解決するんだったら簡単なんです、ある意味では。ところが問題なのは、3型の相談というのがあるんです。専門知識と心理相談の両方がからんでいるんです。だから相談は難しいんですね。
それで、カウンセリングというのは、援助する場合には、直接生身の人間に接しながら相手を援助していく。これをヘルピング・プロフェッションと言っているんです。直接触れ合いながら、相手の役に立つようなことをする専門職です。
お医者さんもそうですね。マッサージ師もそうですね。保育所の保母さんもそうですね。面と向き合うて、何らかの方法で対面しながら相手のお役に立つような仕事は、全部ヘルピング・プロフェッションなんです。これの仕事の重要性がどんどん増えて広がっていってる訳です。
医者というのは専門職ということはすぐ分かりますね。医者になるためには、専門的なことについて長期に渡る勉強とトレーニングを受けないと、社会公認の医者は名のれないわけです。そういう専門職化が進んでいます。
学校の先生は、今は免許が無いと教師になれません。そのための専門に教育大学があります。さらに遅れて社会福祉士・介護福祉士も、国家試験を受けなければ資格がもらえない制度になっていますが、カウンセラーというのは一番資格化が遅れているんですよ。
今は、心理的援助で「専門のカウンセラーです」と言ってる人は、もう大学の臨床心理か教育学部の心理専攻みたいな大学院を出ないとカウンセラーとは言えませんね。で、臨床心理士というのはまだ国家試験ではないですが、認定組織がありまして、そこで認定して、かなり権威を持つようになりました。学校カウンセラーというのもやかましく言われましてね、臨床心理士の資格を持ってないと成れない。そういう専門職化が進んでいるんですよ。
ところが、今、それとは別に、おっしゃったようにお寺さんは相談を受ける。で、相談に乗ってるわけですから、駆け出しか素人か知らんけど、やはりカウンセラー的な役目を果すわけですね。そういう意味で、カウンセリングは大事ですね。ヘルピング・プロフェッションに関わる人は、皆カウンセリング的な素養、カウンセリング・マインドと言ったりしますが、必要だということは、もう至るところで言われています。
お医者さんに行ったら、ろくすっぽ顔も見てくれない、脈も取ってくれないで、「おしっこ取ってきなさい」、「レントゲン撮ってきなさい」と検査にばかり回して、データが上がってくるわけでしょ。その上がってきたデータを見ながら「こりゃ、ちょっとポリープができてるな」てなこと言うわけでしょ。いっこも見てくれない。で、患者には「ちょっといいですか?」って、聞いてくれない訳じゃないですか。今は「そんな医者はあかん」と盛んに言われています。
だから医者もカウンセリングの勉強せなあかん、という時代になってますね。その他、先生でも保母さんでも、ということになると、「坊さんも」ということになるわけでしょ。お坊さんも、ちょっとカウンセリングの勉強せなあかんわけですよ。皆さんは、専門知識、教義の知識とか宗旨宗派の専門知識はあるわけですから、こちら(1:情報・専門知識)は今はカットします。問題はこっち(2:心理相談)なんです。
「セラピスト」というのは、「サイコ・セラピスト」で、「サイコ」というのは精神・心理ということですから、「サイコ・セラピー」は「心理療法」ということですね。不思議なことに、心理学者は「心理療法」というのに、医者は「精神療法」といいます。「サイコ・セラピスト」と言ったら、英語では一つなのに、日本語では訳し方が違うから別のものに思うかも知れませんが、要するところ「心理療法の専門家」ということですね。
専門家の間では、「カウンセリングと、サイコ・セラピーと、一緒か別か」ということが論議になってますが、ここはどうでもいい。要するところ、二人の人が体面していて、一方がクライアント。つまり問う方、悩みを打ち明ける方。それに応える方がカウンセラーということになりますね。そして、何か聞いていく、聞いたら応える、という、つまり主に言葉のやりとりを通して、カウンセラーがクライアントの心の悩みに応えていく、という営みなわけです。
お医者さんというのは、医者しか持っていない資格と権限と技術があるわけです。薬を与えたり、手術をしたり、看護婦(士)さんは看護の技術がありますね。専門技術というものを持っているわけです。
けれど、カウンセラーというのは、資格を持っておっても、お医者さんのような薬を与えたりすることはできない。まして手術はできない。看護婦(士)さんみたいなこともできない。それでいて、相手の心の悩みに応えていく、と。それで、少なくても「これでだんだん気持ちが楽になってきました」とか「ひとりでやっていけそうです」という建設的な声が出てくるわけです。本人自身の生命力というか回復力を導き出す、そういう力を持つようなカウンセラーは、聞き方・話し方が良い、ということになるわけです。
すごいと思いません? それはものすごく難しいんですよ。
先ほどの話はご住職や若さんや坊守さんという固定した関係の中での問いと応えですけど、地域なり市民の相談にのっている専門のカウンセラーというのは、いつも、年齢も様々、男か女かも分からない、しかも持ち込む悩みは全部個別的ですね。クライアントを選ぶわけにはいかんわけです。そういう色んな人がやってきても、対応できる能力が要るわけです。
きちっと言うなら、カウンセリングを甘く考えてはいけない。大変難しいんですよ。だから、カウンセラーになろうと思ったら、言葉だけでなく音声言語。話したり、聞いたり。
書き言葉のコミュニケーションもあるけれども、カウンセリングの場面では音声です。クライアントは話し手で、カウンセラーは聞き手です。それで、時には聞き手が話し手に言うこともあるから、言ったり聞いたりを繰り返しながら、一定の時間、40から50分、せいぜい1時間くらいのことで、ずっとやっていく訳です。それをやっているうちに、段々、本人自身の内面から元気が湧いてくる、というか、癒しの力が出てくる、と。そういうことのできる営みをカウンセリングというんです。
それで、その時に、こちら側(1:情報・専門知識)の聞き方と、こちら側(2:心理相談)の聞き方は、聞き方が違わなければいけません。どういうふうに違うのかというと、これは、今私が言葉で説明したらすぐわかるのに、実際にロールプレイをやって体験学習してもらったら、すぐに<いかに難しいか>が分かります。
こちらの方(1:情報・専門知識)の聞き方は、<話している事柄>を聞くんですよ。「ちょっとご相談に来たのは、お爺ちゃんがおるんですが、世話していたお婆ちゃんが先に死んでしもうて、お爺ちゃん一人残ってますけど、頑固で。一人で生きるといいますが、一人では危ないし、何とかなりまへんやろか?」というような相談。ひどいのになったら「うちの親父は子どもの時から可愛がってもらったおぼえはない。このごろ世話やけるようになって、どっかぶち込むところ、おまへんか?」と、こんな荒くたいこと言うんですよ。要するところ「入る老人ホームはあるのか無いのか。それはどこにあって、どんな手続きしたら入れるのか」と、聞きたいわけでしょ。
そういう人の話を聞いているときには、「お爺ちゃん何歳ですか?」、「いつぐらいからボケが始まったんですか?」など、色々聞くことは沢山あります。聞く事柄が。だから事柄中心に聞くことになります。
こちら(2:心理相談)はちょっと聞き方が違う。それは、いま、ここで話している時に、動いている<クライアント自身の気持ち・感情・意味>を聞く。それは、<どういうことを仰りたいのかな?>というような聞き方になるんです。
まあ、ここまでにしときましょか。ここまで頭に入れておいて、さあ、ロールプレイを5分間だけやってみましょう。
![]() : では、私がお婆さんの役で。
: では、私がお婆さんの役で。
![]() : 私が、カウンセラーですか・・・
: 私が、カウンセラーですか・・・
≪A≫ ・・・・・(ロールプレイ内容は省略)
![]() : クライアント役も、悩みを出すのは大変ですね。
: クライアント役も、悩みを出すのは大変ですね。
![]() : 一応、ある人を想定して話ましたから。
: 一応、ある人を想定して話ましたから。
![]() : 今のは、自分が普段受けている相談を、その人の立場に立って言っていただきました。これは非常に意味が大きいのです。それでは、もうひとケースやっていただきましょう。
: 今のは、自分が普段受けている相談を、その人の立場に立って言っていただきました。これは非常に意味が大きいのです。それでは、もうひとケースやっていただきましょう。
≪B≫ ・・・・・(ロールプレイ内容は省略)
![]() : いやー、難しかった。
: いやー、難しかった。
![]() : こうしてみるとマドマーゼル愛さんなんかは、すごいですね(笑)。相談する側に立つと、いろいろ分かりますね。
: こうしてみるとマドマーゼル愛さんなんかは、すごいですね(笑)。相談する側に立つと、いろいろ分かりますね。
![]() : やってみて思ったのは、先ほど「クライアントの方が色々考えて大変ですね」と言いましたが、やはりカウンセリングする方が大変みたいですね。
: やってみて思ったのは、先ほど「クライアントの方が色々考えて大変ですね」と言いましたが、やはりカウンセリングする方が大変みたいですね。
![]() : クライアント役は、ある人を設定すればいいんですよ。やっぱりカウンセラーは大変みたいですね。
: クライアント役は、ある人を設定すればいいんですよ。やっぱりカウンセラーは大変みたいですね。
![]() : では、後で皆さんで一緒にテープを聞いてみて、そこで感じるままを話していただきましょう。これは、専門家から「この場合はどうしたらいいんでしょうか」という答えを聞くのではなくて、やってみてどんな感じがしたのか、ということをそれぞれ感じ取っていく。聞かせてもろた人は<私ならこういうふうに応えるのになー>とか、<ああいうやり方では、ちょっと相談できんだろうな>とかね。<こう言ってみたらどうやろ>とか、感じるでしょう。
: では、後で皆さんで一緒にテープを聞いてみて、そこで感じるままを話していただきましょう。これは、専門家から「この場合はどうしたらいいんでしょうか」という答えを聞くのではなくて、やってみてどんな感じがしたのか、ということをそれぞれ感じ取っていく。聞かせてもろた人は<私ならこういうふうに応えるのになー>とか、<ああいうやり方では、ちょっと相談できんだろうな>とかね。<こう言ってみたらどうやろ>とか、感じるでしょう。
で、やってみて、当事者になってみて、実感がどうだったのか。そんな話合いをやって、聞いていた方の感想を聞いて、皆で分かち合いをやると、色んなことを気付かせてもらえるんじゃないかと思います。知的に一方的に「こうしたらいいんですよ」、「それはいけませんよ」と指導するよりも、自分でやってみて、どんな感じがするのか、というようなところに触れてみる。そういう学習会です。これを体験学習といって、それの方が、身体で気付いていくことが多いようなんですね。
日ごろ自分が応える立場なんだけど、クライアントの身になってみて相談を持ちかけた。それに対してこのカウンセラーは色々応えてくれたんですが、その応えてくれ方は、どんな感じでしたか?
![]() : 私も実際、ああいう風に答えて言うんですけど、<これじゃいかんな>という感じです。これが聞きたいんじゃない、と。私は、ある具体的な人をイメージして聞いたんですね。それで、私も同じようなことを言ったかな、と思うんです。で、<あ、これは伝わってなかったな>というか、そんなことを聞いているんじゃないよ、と。
: 私も実際、ああいう風に答えて言うんですけど、<これじゃいかんな>という感じです。これが聞きたいんじゃない、と。私は、ある具体的な人をイメージして聞いたんですね。それで、私も同じようなことを言ったかな、と思うんです。で、<あ、これは伝わってなかったな>というか、そんなことを聞いているんじゃないよ、と。
つまり、こちら近辺に引っ越してきて、仏壇屋とかお寺がある。で、一般的に暗いイメージがある訳ですよ。死のイメージですね。結局、そのお婆さんは孤独だったんでしょう。それで余計に孤独感に苛まれる。それで、お寺というのも仏壇というのも死をイメージする。だから、非常に不安な気持ちがあったわけですね。
その不安な気持ちをいかにくみ取れるか、というところだろうな、と。私はくみ取ってなかったし、今回も、ちょっと「仏壇はいい物ですよ」とか「お寺は人生にとってプラスです」ということは、最終的に自分が気付けばいいんでしょうけど、ただそう言われただけでは、<私はそういうつもりで聞いたんじゃないよ>と。自分の気持ちが相手に伝わってなかった、ということを思いました。
だから、仏壇の問題ではないんですね、結局。仏壇が嫌とか、お寺が嫌ではなくて、まず、自分が孤独ということですね。だから後で、「自分の娘も娘婿も自分の思いを分かってくれない」ということが出ますよね。それで、孫だけが小さいから寄ってくる、ということで、孤独な立場だったなあ、と。それが、自分が相談を受けた時の相手の心理状態ですね。「誰も私の相手になってくれない」という気持ちがまずあったんですね。それにどう応えたらいいのかまだ分かりませんけど、気持ちだけは今は分かります。でもその時は分からず、いいアドバイスはしてなかったですね。
![]() : 立場が代わって自分に持ちかけるような、Bさんとしましょうか、Bさんの身になって、一度クライアントになって質問を打ちあけてみたんだけど、<私も同じような答え方をしてるな>と。でもそういう答え方をしてもらったのは、あんまり援助的というか、役にたってる、助けられている感じじゃない、と。クライアントの心の奥に、何か<誰も受け入れてくれない>とか<寂しい>とか、色々な感情があるんじゃないか、ということですか。はい、ではカウンセラー側はどうでした?
: 立場が代わって自分に持ちかけるような、Bさんとしましょうか、Bさんの身になって、一度クライアントになって質問を打ちあけてみたんだけど、<私も同じような答え方をしてるな>と。でもそういう答え方をしてもらったのは、あんまり援助的というか、役にたってる、助けられている感じじゃない、と。クライアントの心の奥に、何か<誰も受け入れてくれない>とか<寂しい>とか、色々な感情があるんじゃないか、ということですか。はい、ではカウンセラー側はどうでした?
![]() : よくある質問なんですけど、ポンポン質問が飛んできますんで、どうしてもそれに対して、一つ一つ答えていかなければならない、と。答えを出していかなければいけない、という義務感というか責任感が出ました。それと同時に、責任のがれ的な話。なるべく自分に負担がかからないような形で、「私が何かしてあげましょうか」ということではなくて、「近くにお寺があるから近くに行かれては」とか、実際お坊さんが前にいるのに、本来なら私が何かをしていかなければいけないのに、仏さまだとか、隣のお寺さんが、とかいった責任のがれをしているな、ということを感じました。
: よくある質問なんですけど、ポンポン質問が飛んできますんで、どうしてもそれに対して、一つ一つ答えていかなければならない、と。答えを出していかなければいけない、という義務感というか責任感が出ました。それと同時に、責任のがれ的な話。なるべく自分に負担がかからないような形で、「私が何かしてあげましょうか」ということではなくて、「近くにお寺があるから近くに行かれては」とか、実際お坊さんが前にいるのに、本来なら私が何かをしていかなければいけないのに、仏さまだとか、隣のお寺さんが、とかいった責任のがれをしているな、ということを感じました。
![]() : そうすると、あなたが、これまでの日常経験でも、ああいうタイプの、ポンポン質問してくる人はよくある、と。そういうふうに質問されると、ひとつひとつ、きちっとまず答えてあげなければならない、と思うので、ああいう対応になった、というのがひとつ。で、そう答えながら、相談しに来てるんだから、私自身がちょっとしっかりと何とかしてあげなきゃいかん面があるだろうに、何か心のどこかに、逃げというか、人の方にふってる、無責任みたいなものがあるなー、ということに気付かれたわけですね。やられて気付かれましたか? 日頃も感じてます?
: そうすると、あなたが、これまでの日常経験でも、ああいうタイプの、ポンポン質問してくる人はよくある、と。そういうふうに質問されると、ひとつひとつ、きちっとまず答えてあげなければならない、と思うので、ああいう対応になった、というのがひとつ。で、そう答えながら、相談しに来てるんだから、私自身がちょっとしっかりと何とかしてあげなきゃいかん面があるだろうに、何か心のどこかに、逃げというか、人の方にふってる、無責任みたいなものがあるなー、ということに気付かれたわけですね。やられて気付かれましたか? 日頃も感じてます?
![]() : 今やって気付きました。
: 今やって気付きました。
![]() : やってみて気付けていく、ということが、すごい力になるんです。やってみて初めて、日常・今まで気が付かなかったことが分かる。普段は答える側にいるけど、尋ね役になってその人を演じてみたら、返ってくる返事は、カウンセラーに自分の気持ちが受け止められたという感じがしない。ああいう答え方ではちょっとまずいんじゃないかな、ということで、つらつらおもんみるに、「暗い」とか「どうすればいいか」と聞いてきているようにみえるけど、複雑な気持ちが動いているんじゃないか、と、見えてきたということで、よろしいでしょうか。
: やってみて気付けていく、ということが、すごい力になるんです。やってみて初めて、日常・今まで気が付かなかったことが分かる。普段は答える側にいるけど、尋ね役になってその人を演じてみたら、返ってくる返事は、カウンセラーに自分の気持ちが受け止められたという感じがしない。ああいう答え方ではちょっとまずいんじゃないかな、ということで、つらつらおもんみるに、「暗い」とか「どうすればいいか」と聞いてきているようにみえるけど、複雑な気持ちが動いているんじゃないか、と、見えてきたということで、よろしいでしょうか。
![]() : そうです。
: そうです。
![]() : カウンセラー役をして気付かしてもらったのは、ああいうふうにポンポンと矢継ぎ早に質問してくる場合は、丁寧にひとつひとつ答えていかなくてはならない、あげたい、という責任感というか、義務感があるんで、ああいうふうに言った、と。けれども答えながらも、ちょっと逃げてるかな、ふってるかな、という感じもあるかな、と。
: カウンセラー役をして気付かしてもらったのは、ああいうふうにポンポンと矢継ぎ早に質問してくる場合は、丁寧にひとつひとつ答えていかなくてはならない、あげたい、という責任感というか、義務感があるんで、ああいうふうに言った、と。けれども答えながらも、ちょっと逃げてるかな、ふってるかな、という感じもあるかな、と。
そこまで話が出たところで、じゃあ、「ちょっとまずかったな」というところを、もう一度聞いて、それよりましなカウンセリングを目指してみたいのですが。
それより先に後半にやってもらった人の感想を聞きましょう。
![]() : 私の場合は、実際とは少し設定を変えて話しました。本当は会社ではないのですが、問題点は同じです。友だちは経済的に弱い立場で兼業なんですが、女性の方は、「結婚したらそっちの方はやりたくない」と言うんです。でも実際の状況は、そんな悠長なところではありませんから、女性の意向に添うことはできそうにない、という悩みです。
: 私の場合は、実際とは少し設定を変えて話しました。本当は会社ではないのですが、問題点は同じです。友だちは経済的に弱い立場で兼業なんですが、女性の方は、「結婚したらそっちの方はやりたくない」と言うんです。でも実際の状況は、そんな悠長なところではありませんから、女性の意向に添うことはできそうにない、という悩みです。
私も同じ立場としての見方ができ、男としての考え方もわかります。私も相談を受けて、今回と同じように話しが詰まってしまいました。助言してあげられないところが沢山ありました。それで、前回も同じことを申したかも知れませんが、相談に乗る中で、宗教家としての自分の立場と、一人間としての自分が交差してしまう。それがうまくスイッチを入れ替えられない自分がいますので、なかなか彼が求めている答えを100%出してあげられないのが自分の現状であると痛感します。
![]() : 今ここでロールプレイをやったプロセスの中では、どんな感じがしたですかね? 「これでは満足できない」とか。
: 今ここでロールプレイをやったプロセスの中では、どんな感じがしたですかね? 「これでは満足できない」とか。
![]() : やっぱり、多分・・・失礼な言い方になってしまいますが・・・何一つ答えが見つからない。かえって頭をかかえてしまう(笑)。
: やっぱり、多分・・・失礼な言い方になってしまいますが・・・何一つ答えが見つからない。かえって頭をかかえてしまう(笑)。
![]() : カウンセラーも困ってはるんやなー、と。
: カウンセラーも困ってはるんやなー、と。
![]() : <相手のことを思って、色んなことを考えてくれはるんやな>ということは感じましたし、<一生懸命になってくれはるんやな>とは感じましたけれど。
: <相手のことを思って、色んなことを考えてくれはるんやな>ということは感じましたし、<一生懸命になってくれはるんやな>とは感じましたけれど。
![]() : 一生懸命に聞いてくれるけど、話せば話すほど困ってはる、と(笑)。
: 一生懸命に聞いてくれるけど、話せば話すほど困ってはる、と(笑)。
![]() : そうですね。
: そうですね。
![]() : ということは、例えばこれは5分間で切りましたけど、これが40分、1時間と続いたら・・・5分間でもかなりしんどい、と。・・・カウンセラーやってみて、どうでした?
: ということは、例えばこれは5分間で切りましたけど、これが40分、1時間と続いたら・・・5分間でもかなりしんどい、と。・・・カウンセラーやってみて、どうでした?
![]() : 難しいですね。どう導くかということですね。自分なりの答えを言うのか、それとも言わずしてもう少し聞いてみたらいいのか。そう考えていると、自分の言葉が出ず、訳の分からない状況になってしまうので、簡単なことなら聞いた時に言えるんですが、それでは自分の考えの押し付けになっちゃうから、聞かれていることから、自分なりの考えを導かせようとすると、どういうふうに聞くのか、どういうふうに返せばいいのか、非常に言葉が難しくなってきます。
: 難しいですね。どう導くかということですね。自分なりの答えを言うのか、それとも言わずしてもう少し聞いてみたらいいのか。そう考えていると、自分の言葉が出ず、訳の分からない状況になってしまうので、簡単なことなら聞いた時に言えるんですが、それでは自分の考えの押し付けになっちゃうから、聞かれていることから、自分なりの考えを導かせようとすると、どういうふうに聞くのか、どういうふうに返せばいいのか、非常に言葉が難しくなってきます。
「そんなら無理だから、別れて他の人を探した方がいいですよ」と押し付けちゃうと、簡単に言葉は出ますが、それを、本人の中で結論が出るようにする、となると言葉が出なくなって難しいな、と思いました。
| ≪≪ [back] | [next] ≫≫ |