先ほどやっていただいた中にも出ていると思いますが、相談を持ちかけている方は、何らかの意味で解決しなくてはならない、してほしい何か心に持っているんですね。「それに応える力はカウンセラーには無いんだ」と、彼はいうんです。どこにあるのかというと、「本人自身しかそれに気付いて解決することはできないんだ」という厳しい見方が前提になっているんです。
平成アーカイブス <研修会の記録>
以前 他サイトに掲載していた内容です
|
9月27日勉強会3 [講師:西光義敞先生]
![]() : 現代のカウンセリングの考え方を提唱したのは、皆さんご存知のカール・R・ロジャーズ(Carl R. Rogers)という人なんですね。この人は、それまでの常識的なカウンセリングの考え方を180度転換した人や、と言われているんです。
: 現代のカウンセリングの考え方を提唱したのは、皆さんご存知のカール・R・ロジャーズ(Carl R. Rogers)という人なんですね。この人は、それまでの常識的なカウンセリングの考え方を180度転換した人や、と言われているんです。
先ほどやっていただいた中にも出ていると思いますが、相談を持ちかけている方は、何らかの意味で解決しなくてはならない、してほしい何か心に持っているんですね。「それに応える力はカウンセラーには無いんだ」と、彼はいうんです。どこにあるのかというと、「本人自身しかそれに気付いて解決することはできないんだ」という厳しい見方が前提になっているんです。
クライアントは悩んでいるから来るんですね。自分でどうしていいのか分からんから相談しに来てるわけでしょ。そうすると、それを聞く方のカウンセラー、セラピストは、聞いてやりながら、どこに問題があるか聞いて、理解し、早く助言してあげたい、あげなくてはならない、答えを出してやらなくてはならない、そういう衝動に駆られるんですよ。
ところが、厳しく言ったら、そんなもん出せるわけがない。だからクライアントが「どうしたらいいのでしょうか?」と聞かれても、何も教えてあげることも、指示してやることも、解決してやることもできないんだ、と。
ところが、それまでは、専門家のセラピストやカウンセラーが、聞いてあげて、聞いているうちに、何で悩んでいるのか暗黙のうちに頭の中で分析したり、解釈したり、原因を詮索しながら、大体聞いたら、「こうしたらどうですか」と答えるわけです。それがカウンセリングやサイコ・セラピーやという常識が頑固としてあったんです。
ロジャーズさんは、「それは基本的に間違っているじゃないか」と。そういう意味で、今までの考え方を180度ひっくり返した理論を打ち立てたわけです。そうすると、カウンセラーは、今までのやり方とは違った聞き方・受け止め方をせんといかんというわけです。それを初期の頃は「ノン・ディレクティブ(non-directive)」と言ったんです。
「ディレクティブ」というのは「指示する」という意味です。答えてあげる。教えてあげる。解決策を指示してあげる。その他には、励ましてあげる。慰めてあげる。「そんなことしちゃダメですよ」と禁止する。「こりゃー、いいんじゃないですか」と勧める方法もある。全部ひっくるめて、カウンセラー、セラピストの方がべらべらしゃべって言うことを「ディレクティブ」といってました。今までのことは、全部ディレクティブだ、と。
そういうことをやればやるほど、本人自身しかわからないこと、本人自身しか解決つかない問題に、本人自身がしっかり取り組む姿勢を失ってしまう、と考えたんです。だから、何か言ってあげるのがカウンセリングじゃなくして、聞くということ。クライアント中心療法。
ところが、普通は聞いてませんよ、ほとんど。ちょっと聞くと、すぐカウンセラーになった人がペラペラと喋りすぎる。少なくとも、聞いて聞いて聞いた上で話すならいいけど、ひとこと言ったら、すぐひとこと答えてあげなくてはならない、と思って言ってるでしょ。これが実は援助的ではないわけです。
「どうしたらいいんでしょうか?」というのは、ここ(2:心理相談)で聞いているんでしょ。ところがこっち(1:情報・専門知識)の聞き方をやっとるわけです。そうじゃないんですよ、という基本原則を知ってもらおうと思って、こっち(1:心理相談)の聞き方がありますよ、と。色々からんでるから、こういうこと(1)を聞いているようにみえるけど、話していることがらに答えちゃダメ。そうやなしに、どういう気持ちなのか、どこまでも、いまここの話しているクライアントの気持ちや感情の意味はどこにあるのか、というところに焦点を当てて聞く。ここがまずポイントですね。
先ほど、やってみて思われたことは、「クライアントになってみて初めて分かったけれど、自分の本当の気持ちをカウンセラーに理解するように話するのは難しい」と。今の自分がよくやっているようなやり方でカウンセラーは話してくれたけれど、ああいう答え方ではちょっと満足できないんじゃないか。つくづく思うのは、クライアントはそこに色々な感情が動いていて、それがたまたまああいう尋ね方になってるだけじゃないか、と。だから話していることがらに答えてしまったら、もうそこで話は引きづられていきますね。
だから、<答えてあげよう>、<教えてあげよう>と、こちらが発言することはちょっと控えて、聞いてみなけりゃ分からないから聞いてみよう。それで「・・・うん。それでどんな気持ちですか・・・どうですか」と、とことん気持ちを聞くようなつもりで、話をとらないで、できたら一区切りつくまで、とことん傾聴、傾聴、傾聴、傾聴、というような聞き方をしたらどう変ってくるか。こういうことだと思います。
それで、ちょっと、初めのところだけテープを聞いてみましょう。再生してください。
――15秒程<内容省略>――
はいストップ。
「嫌な感じがするんですけど。こんなところに住んでいいんでしょうか?」とクライアントは言ってるわけでしょ。ここでカウンセラーは、「嫌な感じがなさるんですか」と、これでいいじゃないですか。感じだから。本人の感じだから。「嫌なところに住んでる、住むの嫌だなー、と、そんな感じですか」と、受け止めたら、こちら(2:心理相談)の聞き方、共感的な聞き方です。
ところが早々と「それは良いことですね」と、こう出ましたね。これで「良いこと」というのは、カウンセラーの立場の価値判断で言うと、「それは良いことだ」、「悪いことだ」と。ひとこと言ったら「それは良い事ですねー」、「あ、それはいけませんよ」、「それは感心ですね」と言って、こちらの評価ばかりを相手に押し付けることになるでしょ。そうすると、後だんだん出しづらくなるんです。
だからできるだけ、まあ初めは難しいでしょうけど、カウンセリング的援助というのは、何か言ってあげることで解決するんじゃなくて、傾聴してあげること。「あげる」というのも問題やけどね。聞いて聞いて、とことん<何をおっしゃりたいのか、どういう気持ちを今ここで言葉にし始めているのか>を傾聴していく。それがカウンセリング的聞き方であり、そういう聞き方をしてくれるのをクライアントは望んでいるんだ、と。こういうことですね。
だから、初めの5分間どころか、1分間ほどのカウンセラーの受け止める態度を分析してみたら、カウンセラーが「それはいいことですね」と、解決策以前にカウンセラーの方の価値判断をポンポン投げかけている、ということですね。これが今のところのカウンセラーの態度になっているんですが、そういう態度を改めていくことが、カウンセリングの勉強になります。
しかし、今のところは理論も何も知らんわけですから、もうちょっと聞いてみましょうか。
――1分程<内容省略>――
少し質問したら、あれだけ助言が返ってきたわけですが、これは、どんな感じでクライアントとしては聞かれましたか? 彼の懇切丁寧な、具体策までを教えてくれた助言ですが。
![]() : 最初に気持ちが入っていれば「そういう会もあるのか」と次にいけると思うんですが、既に壁があるから、入る気持ちにはならないでしょうね。おそらく、最初に受け止めてもらうと、そういう会の話も、もしかしたら乗ったかもしれないけど、おそらく乗ってこないだろうと、私がそのお婆さんの立場では。
: 最初に気持ちが入っていれば「そういう会もあるのか」と次にいけると思うんですが、既に壁があるから、入る気持ちにはならないでしょうね。おそらく、最初に受け止めてもらうと、そういう会の話も、もしかしたら乗ったかもしれないけど、おそらく乗ってこないだろうと、私がそのお婆さんの立場では。
![]() : カウンセリングでは、スタート段階がものすごく大事だ、と言われているんです。基本的な聞く態度が決ってしまうんです。ですから、これではどれだけ続けても同じようなパターンになってしまうでしょうね。
: カウンセリングでは、スタート段階がものすごく大事だ、と言われているんです。基本的な聞く態度が決ってしまうんです。ですから、これではどれだけ続けても同じようなパターンになってしまうでしょうね。
カウンセラー自体は良い事を言ってるんです。親切に紹介しています。ところが、そういうことを聞きたいな、という気持ちになっているんかどうか。それを確かめずに一方的に「婦人会に入ったらどうですか」と言ってるわけですが、そのへんのところ、「何か良い会があるんでしょうか?」と、質問が出て答えるんやったら意味があるけど、何も尋ねてもお願いもしてないのに紹介していることは、<それはそうか知らんけど>という気持ちでクライアントは聞いて、<私の言いたいのはそういうことではなくって>と思うでしょ。
ということは、そういう事柄を聞いて、情報提供してもらうことに感心があるんじゃないわけですよ。だから、クライアントの気持ちを言い切らないうちに、カウンセラーが色々言ってはるけど、<もうちょっと聞いて>という気持ちになってると思うんです。
これは文字に直したらよく分かるんですが、いいカウンセリングになってくると、クライアントがずっと喋ってる。カウンセラーは、「うん」、「そう、辛いの」、「なるほど」、「こんな気持ちなんですね」と、ちょっと受け止めるだけでね、できるだけ喋らないようにして、相手が話しやすいように、気持ちが出しやすいように、と継続し、5分が10分、15分と続けていく。
カウンセラーが早々と解釈したり分析したり、カウンセラーからの立場からの価値判断をしたりすると、クライアントはものが言いにくくなってくる。<私の言いたいことはそういうことじゃなくて>と、カウンセラーの親切に言ってくれることが、全部<いや>、<そうじゃなくて>、としか入ってこなくなるので、<あかんなー。もうちょっと聞いてくれるかと思ったけど。もうよろしいワ>と、あきらめムードになってしまうんですね。
ですからこれは、いろはのいやけど、こちらの価値観を相手に伝えること、教えてあげること、慰めること、全部ひっくるめて、ディレクティブな方法はちょっと棚の上にあげて、聞き役に徹してやろう、という態度で、話しやすいように「それで」、「なるほど、なるほど」、「ああ、そうか。何かうっとうしい感じなさるのね」と言ったら「そうなんですよ」となる。
「そうなんですよ」とクライアントが認めてくれるような聞き方になると、気持ちを受け止めたということになります。それで、受け止めてもらえたら、次の気持ちもまた出しやすくなってきます。それが出せないままに、今のケースはずっと終っていきました。
そういう意味では、ちょっと場面は違うけど、2番目のケースは、丁寧に「もうちょっと聞かせてください」という感じだった。これはいいと思うんですが、<どこかで答えてあげねばならない>と、心のどこかにあって、でも聞けば聞くほど難しいし、どう言ってあげたらいいか分からないから、だんだん追いつめられていくケースです。
5分間でもう追いつめられてるんだから、続くわけがないんです。でもその時にも、あなたの問題はあなたの問題です。自分が代わってあげることも、解決してあげることもできないんだ、という、有る意味では当然、有る意味では厳しい選択をふまえた上でカウンセリングを始める方が、こちらも気が楽だし、上手くいく。
「ちょっと聞かせてもらうだけでは、とても解決できる力はないんですけど、どういうことで困ってらっしゃるのか聞かせてもらいながら、ご一緒に考えさせてもらえるぐらいだったら私はできるんですけど、そんなんでいいですかね」と、いって初めにカウンセリングの限界を申しあげて、聞いていくと、案外時間が続いていきます。
今回のことは、ひとつの教材としてください。次にカウンセリングする時は、だいぶ変ると思います。また横で見てる人は、人がやってるのを見ると簡単そうですが、自分が体験して気付いていくことが大事です。次回は多くのパターンをやってみましょう。
![]() : 本人が専門知識のみを理解しようとしている場合は、カウンセリングの立場で受け止めていたら、答えにならないですよね。そういった見分け方はどこでしたらいいんでしょうか?
: 本人が専門知識のみを理解しようとしている場合は、カウンセリングの立場で受け止めていたら、答えにならないですよね。そういった見分け方はどこでしたらいいんでしょうか?
![]() : 明らかに専門知識を求めている場合は、心がスカッとしておれば、例えば「日照権はこういう状態でもめているんだ」というようなことを丁寧に知的に説明するわけでしょ。「隣にごっついビルが建ったんで、日が射さなくなった。それで家族が次々に病気があるんで、これは泣き寝入りしていいのかどうか」と。これは法律知識で境界とか相続とか離婚とか、法律にからんでるのは、法的に解決する方法を聞いたら、からっとするじゃないですか。それで済むなら、それで一件落着です。
: 明らかに専門知識を求めている場合は、心がスカッとしておれば、例えば「日照権はこういう状態でもめているんだ」というようなことを丁寧に知的に説明するわけでしょ。「隣にごっついビルが建ったんで、日が射さなくなった。それで家族が次々に病気があるんで、これは泣き寝入りしていいのかどうか」と。これは法律知識で境界とか相続とか離婚とか、法律にからんでるのは、法的に解決する方法を聞いたら、からっとするじゃないですか。それで済むなら、それで一件落着です。
それは専門家のところへ行かなければ解決がつきません。そういう相談も沢山あるわけです。そういう意味の相談員になろうとしたら、それぞれ専門領域の勉強をしょっちゅうやって、法律相談だったら法律の勉強。僧侶も専門の勉強は大事ですね。
「地獄・極楽なんてあるんですか?」とか「納骨せんならんのですけど、あれはどれくらいお仏壇に置いておいたらいいんですか?」とか、そんな具体的なものが出てくるじゃないですか。それはそれなりに答え方というものがありますよね。また一概に答えられない面もあるけれど、色々なケースを知っておったり、本願寺派では、とか、名古屋地方では、ということがあって助言してあげたら「はあ、わかりました」で済む場合もあります。それはそれでいいと思います。問題は3型。『情報・専門知識』と『心理相談』が絡んでる問題です。
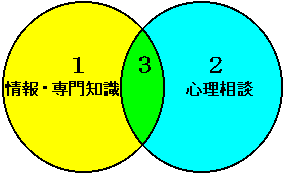
今のでいきますと、「何かお寺は暗い感じだな」と、「こんなところに住んでいいんですかね」というような言い方をしているけど、「一般的に仏教は暗い」とか、「こんなところに住んでていいのか」という「こんなところに」というのは、どんなところなんか知らんけど、そういうものの言い方で、それに答えてほしいんじゃなくて、いみじくもやってみられて気付かれたように、こういうことを言う人は、寂しいとか、仏教に反発を感じているとか、何らかの意味の心理的な悩みがあるんですよ。
それが一体何かのか、それをきっちり理解することが援助的だな、と思ったら、それを受け止めていく。クライアントは次から次へ心理的なものを受け止めてもろたら、<この人は聞いてくれる。話ししやすい>と思い、次から次に思いを出すようになるんですね。
ですから、初め出した問題は、聞きたいことではなくて、本当は心的なところを聞いてほしいということです。これは、真面目にカウンセリングを学んでもらえばすぐに体験することです。
僕が駆け出しの頃、平安高校でカウンセラーを始めたんですが・・・<内容省略>・・・相手の言うことをそのまま受け止めていたら、次々と話が進んでいきました。初めにこちらが答えを出していたら、こんな深い問題は出てきません。だから、先ほどのケースでも「私も辛いですわ」という方向に進んでいけば、初めの問題はどうでもよくなります。
Aという質問をしたらすぐ答える、じゃあBという質問をしたれ、というふうでは悩み相談ではなくなってしまいます。<気持ちを聞いてよ>と言っているんだと思います。
その時に、自分の気持ちを言葉にして伝える能力は皆あるわけではないんです。それは難しいんです。自分の深い悩みを言葉にして聞いてもらう、ということは。
だから最初あたりは別の話をするんです。それを、「そんなことはないですよ」とか「仏教婦人会があります」というのは、ちょっと勇み足です。クライアントにしてみれば、そこまで聞きたいと思っておらんことを、こっちがついつい言うわけやから。
ずっと聞き込んでいって、時間がきたら「お約束の時間がきましたので」と切ったらいいんです。それで「よかったら来週、ご都合がよろしい時に」と言うと、<聞いてもらって良かったな>と思う人は「また来週お願いします」とかいう形で続いていきます。
次回は、今日やっていただいたのを手がかりに、もうちょっと掘り下げて聞いて、今日よりはちょっとましな聞き方ができるんじゃないかな、と思うし、時間があれば、他のトレーニングの方法もご紹介します。
| ≪≪ [back] | [next] ≫≫ |