報道されだけで年間140ケースあります。これは大人の暴力によって児童が亡くなっているんですね。データとして私たちが知りうるものはこれ位しかないのですが、これは起訴された分だけです。当然起訴されなかったり、虐待として扱われなかった児童の死亡例というのは、この5〜6倍はあるだろう、というふうに考えられます。
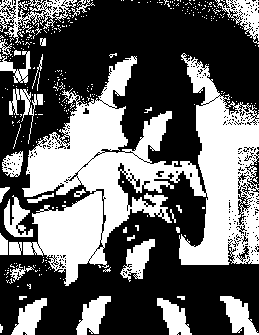
平成アーカイブス <研修会の記録>
以前 他サイトに掲載していた内容です
|
[講師:子どもの虐待防止ネットワーク・愛知 理事長 祖父江文宏 師]
(先生は平成14年6月1日に逝去されました/享年62歳)
私たちCAPNA[キャプナ]の活動の中でも、これは重要な仕事だと思っていますが、電話相談と並んで『調査研究部』というのがあります。この中で日本の虐待死のデータを出しています。第1回に『見えなかった死』という題をつけました。それから去年の12月に『防げなかった死』。今年の12月にも1冊出しますが、それは日本における児童虐待で新聞に報じられたものを全部集めた本です。
報道されだけで年間140ケースあります。これは大人の暴力によって児童が亡くなっているんですね。データとして私たちが知りうるものはこれ位しかないのですが、これは起訴された分だけです。当然起訴されなかったり、虐待として扱われなかった児童の死亡例というのは、この5〜6倍はあるだろう、というふうに考えられます。
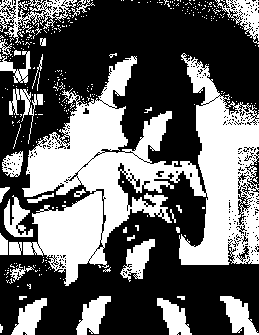
例えば0歳の人たちの死亡例の中に、<突然死症候群>だとか、シェイクンベイビー<揺さぶられっ子症候群>という形で報告されています。あるいは、内臓破裂だとか脳膜下出血・頭蓋骨内出血・頭蓋骨骨折・窒息死・水死・そういう形で報告され、事故として扱われたものの数というのは相当膨大です。小さい人たちの死亡例の中では、事故として扱われた数が最も多いんです。病気よりも事故の死亡例や別の診断が付けられたものの方が数が多い。
これは絆といったらいいですかね、そういうものが引き起こしてくる暴力。これは家族特有のものです。ですから通常の<開かれている家庭>には無い、非常に特異な形の暴力構造がおきてまいります。それは私たちの知る限り、その家族の3代4代にわたる病理であると考えます。それは密室化され温存され続けてきた暴力関係です。
その暴力は必ずエスカレートしてきます。しかもそれは「暴力的である」と誰かが外側から意識したり、家族の誰かが指摘すると、それは加速度的にさらに悪い方向に向きます。そういう時に小さいいのちが危険にさらされるのです。
アメリカではゴールデンタイムにこういうコマーシャルが流れています。――「子どもの死亡原因で最も高いのは交通事故ではありません。病気でもありません。それは大人の暴力によってです」と、こういうコピーの後で必ず次に出されるのが前年度の全米の虐待死の数字です。その時に出てくるのは、「全米では1日に5人の割合で大人の暴力によって子どもの命が奪われています」というふうにいいます。
このことについて日本では、「アメリカだけが特別だ」という言い方をしてきました。日本には虐待死は無いということになっていた。ところが私たちは10年ほど前から、「どうしても見過ごす訳にいかない現実がある」ということで調査・活動を始めました。
大人の暴力によって死亡したり傷ついていった子、そして身体的な傷にとどまらないで心に大きな傷を負った子、つまり外側から加える暴力の不当性の中で、自分の正統性を抹殺されてしまった子。これは人権を踏みにじられるわけです。そうすると自分というものに価値を全く持てなくなってしまう、つまり自分を大切なものとして考えることができなくなってしまいます。さらにそれは自分という根拠を消し、自己を破壊されてしまう。そういうものが虐待という暴力である、ということがだんだんに分ってきています。
これはPTSD「心的外傷」という言い方をします。最近の精神医学のところでは非常に市民権を得た言い方になってきています。僕が知る限りPTSDがNHKのニュースで流れたのは、去年の夏の武豊の花火工場の爆発の時に「心的外傷」という言葉が使われました。
実はこの言葉が出てくる素地は阪神淡路の大震災ですね。あの時被害にあった子どもたちの問題をやっていくときに、丁度アメリカでPTSDという言い方をし始めていました。それは「暴力による心の傷というものがあるのだ」ということを、もう一度はっきりとアメリカの子どもの問題として提示し始めたとき、「もう一度」ということは前例があったんです。
素地としては虐待問題は新しい分野で、全米でも「虐待が親によって暴力が加えられるんだ」ということが社会的なコンセンサスを得るのは20世紀半ば過ぎなんですね。それまでは「大人が子どもに暴力を振るう事はない」、「まして親は子どもを傷つけることはない」、そう言い切ってきたんです。言い切ってきたということは現実に目をつぶってきたということです。
それが1950年代になって現実に傷ついた子どもたちが見え始めてきた。それを最も端的に見たのはレントゲンによる傷の証明です。古い傷が見つかる。虐待で傷を受けている子をレントゲンにかけてみると、古い傷が確実にある。虐待というのは繰り返される暴力ですから、一過性のものではないです。ですから阪神淡路大震災のときのものは一過性のものですよね。ですから虐待とは言わないわけです。
虐待は繰り返された暴力、それも大半は特定の人間による暴力です。この傷がどうなるのか、1950年代でははっきりしていなかった。1960年代になって、現在のような「心の傷」として、それが今生きて行くのにどんなに重いものになっていくか、ということを証明した。つまりそういうPTSDといわれる心的外傷がひとつの<生き難さ>の原因になる、ということを見せた医者がいたわけです。これはケンプという小児科医が1962年に出した論文、『バタードチャイルドシンドローム(被虐症候群)』にあります。それは現在でもほとんどの医学部の指定教科書に出ていますが、それから以降、「子どもの問題だ」と言えなくなってしまう症例が起きてきました。
アメリカの20世紀は常に世界の戦場に向っていった。その中で、一人の心の問題ではなく社会の問題として対応せざるを得ない反社会的な行動が、サバイバーと言いますが戦争で生き残った兵士たちです、その戦場から帰還した兵士たちによって全米でいくつかの事件が次々起きてくる、ということがありました。それはベトナム戦争です。
圧倒的な軍事力によってアメリカがベトナムの戦争に介入し、アメリカの思惑では「ほぼ一ヶ月でかたがつく」とペンタゴンは豪語していたんです。「負けるはずない」と。ところがご存知のように、結局アメリカは負けたわけです。この負けを見事に予言していた人がいたんです。それは北ベトナムのボー・グエン・ザップという将軍です。
彼は「この戦争は兵器においては圧倒的にアメリカが強いだろう。しかし戦争には私たちが勝つ。それはアメリカの兵士たちは自分たちが何故この戦場にいるか分からないからだ」と言います。
戦場というのはいつ命を奪われるか分らない徹底した暴力の世界です。その暴力の世界に自分がなぜいるかが分からない。しかも暴力を受け続ける。北ベトナム、ベトコンと言われる人たちがどこで狙っているかわからない。そういう恐怖。しかも彼らは何のために暴力を受けるか分らない。さらにそれは大きな恐怖を生む。そのとき彼らは自分で判断し自分で行動する能力を奪われる。
これは暴力というものを考える一番根底にあるものです。「暴力がなぜ悪いか」といったら、実はここにあるんです。人間が自分の意志や自分の思考を全く失ってしまうのが暴力なんです。アメリカ軍はそういう状況の中で戦争をしなければならなかった。だから「おそらくアメリカは負ける」と言った。で、その通りになりまして、結局<なぜ私が暴力を受けたか分らない>。そして<戦争に参入した意味も分らない>。そういう兵士たちがアメリカに続々とサバイバーとして帰ってくるわけです。そうすると戦場において経験した暴力性を、社会の中で様々にぶつけてくるわけです。これは、勲章をもらって戦争が終ったらそれで解決するはずだった人間の平和への思い、というものが、実は戦場をくぐったためにその暴力性が温存され続けてきた。さらに倍加された、という証明だったわけです。
これは人間の根底にあるのは実はこの暴力性ではないか、という提示の仕方になっていたのです。これは映画の好きな方々だったら思い当たると思いますが、ベトナム戦争以降のアメリカの映画は極端な変り方をします。それは心理的なものをいつも描いていく。そのときに暴力の中での人間性というものをテーマにせざるを得なくなっていたんです。『タクシードライバー』から『真夜中のカーボーイ』とか『ゲッタウェイ』。また戦争そのものを暴力の体験として捉えなおしてゆくときに『地獄の黙示録』とか、それ以降の一連のベトナム戦争映画が次々出てきます。その中で裁かれてくるのは人間の暴力性です。
平和な時代には無いように見えている暴力性が人間の中に実はあり、特定の状況下では、引き金ひとつ引かれたら、人間は暴力を振るうものになる。人を殺す者になる、という認識です。
これは、もうここまで言えば本願寺の皆様方は親鸞聖人の『歎異抄』――「さるべき業縁のもよほさば、いかなるふるまひもすべし」ということを思い出されると思います。
こういう人間の認識ですね。
浄土真宗と人間の暴力性というものは無縁のものではありません。おそらく僕は親鸞聖人が言い続けられた、あるいは王舎城の中で繰り広げられたあれだけの暴力には、その根底には<人間というものの持っている暴力性、そのことをどう乗り越えていくんだろうか>という問題の提示の仕方がずっとあったんだと思います。このことは、例えば明治の清沢満之の様々な言葉の中にもありますが、いかにして自己の暴力性を超えていこうとするのか、ということを課題にしてきたわけです。
このことは横に置いておいて、アメリカでベトナム戦争をくぐったことによって、人間の持っている暴力性というものをどうしても社会の問題として捉えなければならなくなった。勲章をいくつももらった人たちほど反社会的な行動を繰り返す。そういうことが起きたわけです。
これは当時実際にあった話ですが、映画の中でも時々出てくるベトナム戦争で特殊任務についていた人たちが、帰還後もチームを組み、さらに何かをやるんだ、ということがあるわけです。そしてアメリカの中では本当に人間狩りが行なわれて、最も面白いスポーツとして人間を追い詰めてゆく、そして本当に撃ち殺してゆく、ということがやられていて、そのためのターゲットにされる人間が売買されていた、ということが実際にあるんですね。
暴力ということで言えば、それを性の問題に置き換えれば、アメリカでは幼児に対する性のマーケットが依然として存在しています。これもベトナム戦争から端を発しています。そういった諸悪といわれる暴力というものはサバイバーたちによって大きな社会問題になってきた。その時に初めて暴力というものに人間が直面し、さらに人間の心理的なもの、精神世界というものをもう一度見直してゆこうということがおき始めてきたんです。
そしてその時に解決策として「小さい人への暴力を防がなければならない」、何故かといったら、「暴力は連鎖する」ということがはっきりしてきたからです。
つまりサバイバーたちの心の問題もあるけれど、しかし暴力がさらに問題化されてきたのは、実はその人たちが親になった時に、子供たちの上に出てきた暴力性、子育ての中で親達がやり始めた暴力性、それが問題になってきたわけです。ですからその時に児童虐待という問題をきっちりと防止することしか、暴力化をふせぐ手はない、という捉え方、危機感があったんです。
暴力は大人の論理で行なわれます。大人は必ず暴力を正当化します、ですから小さい子は暴力を受けると必ず「自分が悪い」と言います。「僕が悪い事をしなかったら父ちゃんは殴らんかった」と言います。「私が悪い子でなかったらお父さんは私を犯さなかった」と言います。そうやって自分を消してゆくんです。
「悪い私」、「だから私が私自身を罰する」、「だから私は生まれる価値の無かった者だ」、「だから私は私を消す」という形になってゆくんです。そして「そういう私だから私を消すように周りの者を消してゆく」と、破滅に向ってゆくんです。だから、そういう人の場合、暴力を基準にせざるを得ないのです。それ以外の人間関係を結べなくなるのが虐待の問題なんです。
僕が日本の中で行なわれる様々な犯罪は非常に暴力的だと思います。それはあえて言うと、真宗が力を失った証拠だと思います。それは人間本来の暴力性を見据え、「人間がある状況に入ると必ず暴力を引き出すものだ」という認識をもう一度きちっと作って、そこから人間を見ていかないと、僕はこの暴力的な社会に対応することは多分出来ないだろう、と思います。
それでは具体的にどういうことがおきているか、というと、「暴力を振るう側の論理は、振るわれた者にも必ず移ってくる」ということです。
つい最近の池田の小学校の事件で、僕たちが1番問題にしなければならないことは、あの宅間という人は社会に向ける怒りを、自分が最もくみしやすい人を相手に出したわけです。それは宅間という人の育ちの問題があるでしょうし、それが最も大きな要因だと思いますが、彼にそういう価値観を与えたのは社会だと思います。その社会への憤りを、最も自分がくみしやすい相手、あの学校は高校生や中学生もいるわけです、ところが彼はそこを避けてわざわざ小学校に入って、小学校でも1年生2年生の教室に入っているわけです。つまり彼は最も弱いところを狙ったわけです。
昔は「死は受け入れざるを得ない」ということが語られていたと思います、ところが今は死を受け入れることが全くできなくて、憤りだけがものすごく強いわけです。ですから今、被害者たちの教師に対する怒りは凄まじいものがあります。「お前達が身を呈して子どもたちを守らなかったからいけないのだ」という形での怒りが凄く強くなっています。
これはどういうことかというと、おそらく宅間がやった怒りのパターンと全く同じものが生れつつある、ということです。この中で決定的に見えないものは何かというと、死をどう了解していくか、ということです。つまり「有限の人間が無限の世界にどう生きることができるか」という問題なんだろうと思います。つまりそれは、現代の社会が宗教性を失っている、ということでしょう。宗教の問題は後ほど触れていきたいと思います。
それで1960年以降ですが、虐待を見つけて、そこから小さい子どもを救済していくためには、これはもう個人の問題ではないのだ、社会全体が責任を負わなければならない、となってきた。つまり、リアルタイムで虐待がおきてくる場面で、進行度合いをきっちりと受け止めながら、市民が救済をしてゆく必要がある。これまで行政に任せていたが、行政の中で時間ロスがある。これは残念ながら日本の中の死亡例にはいつもこれがあるんです。
つまりケースワークという形で一人の人を救済する手立てを組む。それは役所の中で書類相手にやっていたんではロスをおこすわけです。役所の機構の中では上司の許可がいるだろうし、最後の最後にいのちの救済をするときに親権剥奪だとか、身分の保全だとか、そういう形で人権を守ろうとしても、それまでの間に、愛知県でいえば知事権限の委譲という書類を作ってハンコをもらわなければならない。出来ないですよね。その間に3日くらいかかっているわけです。この3日の間に殺されないという保証はない。
虐待というのは、ひとたび虐待ということが見えてくると、僕は「3回」と言います。4回目には死体になる。それくらい早いと思っています。
そういう虐待の進展にこれまでの時間ロスを持った行政のやり方では対応しきれないということがあります。このことがアメリカで非常に問題になったんです。「結局救えないではないか」と。そのとき「それではどうするか」といったら、市民がそれに参画する。そして参画しなかったらどうするか。そうしたら罰則だ、と。こういう形でアメリカで1960年以降にいわゆるレコーディングロー「虐待報告義務法」という法律が、カリフォルニア州(1963年)から全米の法律として施行されました。
それは生活場面で起きている虐待を同じリアルタイムで生きている人にその発見を委ねる、そして一気に救済に行く、という形で虐待問題に対処していこうとしています。そのときには基本的には何かといったら、「人は虐待するものだ」ということです。
で、私はこういうことをやりながら、いくつかマスコミとの接点があって、色々な形で関わらざるを得ないのですが、日本のマスコミの中では「鬼のような特別な親がやる」という風にしか虐待を捉えていません。だから「なんであんなひどいことをするんですか」、「鬼みたいですね」と、しょっちゅう言う訳です。
ここが僕はアメリカがクリアしたところなんだと思います。それは人は暴力的な状況の中では必ず暴力に頼らなければならなくなる。それが人間なんだ、ということです。そういう状況の中に人間が追い詰められた時に、人は孤立し暴走する。そういうものだ。それは特別の人間だからやる訳ではない。人間というものの1番基本にこの暴力性がある、という認知の仕方だと思うのです。
今私たちが問われているのは、ここだと思うのです。私たちは本当に親鸞聖人がおっしゃるような「さるべき業縁のもよほさば」ということを真に受け取れるか。そうでない限り、私たちは救済する者にはなれません。
「あれは特別の人です」では、私たちの向こう側の人間を作り出すだけです。それでは<私の生活に関わるもの>、<私の人間性に関わってくるもの>、としてとらえることができなくなります。すると私たちは人間というものの生き方の中につながりを切ってゆくということを意識的にやり始める、と僕は思います。
僕がCAPNA[キャプナ]という市民団体の中で考えているのは、人間をつなぐことだと思っているわけです。人間は孤立した時には暴力に頼らざるを得ない。その時本当に人間と人間の関係を持ちつづけていくことが1番大事なことではないか、というふうに思うのです。
その人間の関係の持ち方の中で、日本だけは宗教的な福祉活動を意識して省いてきたんですね。戦後日本の社会福祉の中で、宗教性というものは全くありません。それはどうして無いかというと、今の憲法の中にうたわれているのは「すべての国民は、文化的な最低限度の生活を営む権利を有する(第25条)」、それに対して「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と社会福祉を作っているわけです。
人間の苦悩や悲しみや、そういうものに対することに手当てをするのが本来の福祉です。ところが今言ったように「国家がその手当てをするんだ」と言った時に、国家・公共であるということは、公共の福祉になります。公共の福祉はどこに視点を置いているかというと、<一般国民>という形で、ある一つの群れを想定しているんです。その中の問題なんです。
ですから公共の福利に反するんだったら、ハンセン病をああいう形で封じ込めていくこともあるわけです。それからアイヌの人たちに対して続けられてきた旧土人法という法律も、そういう形で温存され続けてきたんです。公共の福利に反するからです。それは<大多数の人たち>というものです。ですから「公共の福利」とか「福祉」と国家が言う時は、いっぱい問題がでていますね。
例えば岐阜でありましたね、生活保護を受けている人がリュウマチだった。岐阜市内の病院まで通わなければならない。で、そこから病院に行くのに診療時間に間に合うバスが無いんです。で、彼女は軽自動車を買って、それで通院することにした。ところが、それが原因で生活保護が切られる。どうしてかといったら、「国民全てが軽自動車を持たない限り最低の生活とは言えない」、こうなる訳です。
これは青森で起きたことですが、おじいちゃんとおばあちゃんが孫娘と一緒に住んでいました。孫娘が高校へ行く。その時に大学に生かせてやりたいと思って、おじいちゃんとおばあちゃんは生活保護の中からいくらかづつ貯金していた。そしたら、「これは生活保護の中で、貯金を持っているのは最低の生活ではない。従ってそれを使い切った後でなければ生活保護の支給はしない」ということで打ち切られてしまったんです。
これは国家というものがやっていく時の必然だと思います。それは国家がやる以上、与えるものの論理で与えざるを得ない。それからもうひとつ、与えるというのはどういうことかというと、物の分配です。分配ということは自分のざるの中にどれだけ持っていて、それをいかに公平に配るかということが福祉の形になる。これはパンの問題です。
人間はなぜ福祉を必要とするのか、それはパンだけが充足すればいいのか、という問題です。そうすると「人はパンだけで生きている」と言い切れるだろうか。僕は福祉というものは、人間が根源的に抱える問題、それは死というものをどう了解するか、病をどう乗り越えていくか、病をどう受けとるか、あるいは老いというものをどう受け止めるか、という問題だと思うんです。そこからしか福祉の問題は出てこないんです。
それに対して答える術は国家の福祉では物の分配でしかない。貧しいということが主眼であれば、それはパンの分配で人間の救済はできたでしょう。しかし1番根源的なところでは、パンはなくても心の充足があれば、という世界もあるんです。この問題には日本は答えることが無かった。しかも、これは同じ憲法の中で、こういう条項があります。
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない(第89条)」、つまり国庫からお金を出さない。これは宗教の自由という言い方で言われています。しかしこれ、人間の救済が個人の宗教的な慈善活動や福祉活動でない、と言えますか。つまりこの条項をのんだときに、僕は浄土真宗は死んだんだと思います。つまりもう心の問題に切り込めない。福祉を国に任せることで、人間が心にもった苦しみ悲しみを宗教の世界で本当は答えていかねばならないのに、これをパンの分配ですむと言い切ったんです。
これは本願寺派ではどうか分りませんが、大谷派の中で靖国の問題が云々される。僕はその一番の根っこにこの問題があると思います。宗教の自由という形で言うけれども、実は無宗教しかないんです。福祉という視点でとらえたら、もう人間の問題に答えられないんです。ところが答えているとし、それ以外の人間の救済はないという憲法を私たちは持っているんです。もう浄土真宗が入る余地はないんです。
その中でも「宗教は自由である」という言い方をするんだけれど、宗教の活動面や、宗教を証していくという中では「行」というものがあるはずです。それが立てられないんです。そういう問題を大きく含んでいる。それは公共の福利という形で考えてきた中で、その人たちだけの福利を考えるだけではなく、そうではない人たちの福利をどうするのか。つまり「鬼のような親たち」を作り出す今のシステムに「これでいいのか」という問いかけ。つまりあなたも私もともに人間の1番基本的なところで暴力性というものを持っていますよ、という認識がなかったら、私たちは救済する者になれない。救済する者という立場が宗教的な立場だと思います。
それは善導大師が六時礼讃のところで「かの国に到りをはりて、六神通を得て十方界に入りて、苦の衆生を救摂せん」と、そういうことですよね。つまり回向ということが、浄土真宗の最も大きな行為として裏づけられているのがこのことだと思います。
それがなかったら、現実の力を私たちは持たないんです。それはパンだけで生きればいいんです。だから虐待をした人間を「あれはひどい人間だよ」、それで済むんです。そこで私たちは人間のつながりを断ち切ってしまえばいいわけです。しかし本当に私たちはパンだけで生きられるのだろうか。宗教的な世界を捨て去ったところで私たちは人になっていくという道が断たれたのでは、という問いかけがあります。
ちょっと脱線してしまいました。同業者だとこういう話になってしまいますね。
アメリカの中での「ヒューマニズム」、これは僕は宗教的なものが強かったと思いますね、ヨーロッパのケースワークの中でも、虐待の問題をやりながら最後はどうしても宗教的な救済というものに突き当たっていくわけです。様々な事柄や物的なものを全部保証しながら、最後は人間と人間がどうつながっていけるだろうか、この心の問題に必ず至るんです。
ところが日本のケースワークの中には、さっき言ったように既に国家の福祉は心の問題を切り捨てて余りにも長い年月が経っているんです。だからどうしても一つの手法が行き詰まっても、行き詰まった手法・制度の中で人間の救済をやらなければならない矛盾を背負わされているんです。
例えばハエはハエ取り紙に捕られるものです。で、ハエ取り紙の方が強いですよ。でもハエ取り紙にくっ付いたハエがハエ取り紙を背負って飛ぶなんて発想は全然持てないわけです。でも「人間というものはそれができるよね」ということ。「さるべき業縁のもよほさば」という世界に生きている人間に、しかし信頼を持ちつづけることができるのは、多分僕は「ハエ取り紙を背負って飛ぶハエがいてもいいやないか」という発想だと思いますね。つまり、そうした認識の中で人間救済の希望が見えると思います。
それは多分虐待の問題で20世紀から問われてくる問題だと思います。
具体的に、何が問われるかというと、ヒューマニズムが問われる、というふうに思うわけです。それは「人間のために」・「自由のために」という形でアメリカは戦争に介入し、ベトナム戦争などをし、アフガンでもソビエトが進行する。その時代を支えた「人間のために」という思想、これは自分たちの中の公共の福利、ということで人間をとらえてきた。そのことに多分拠るんだろう。それは明らかに間違いだった、と僕は思います。間違いだったらどこに帰るのか、といったら僕は浄土真宗に帰る、と思っているわけです。
これは、ヒューマニズムという形で捨て去ってきた浄土真宗をもう一度人間の名において解放しなければならない。これは絶対に必要なんだ。それでなければ、本当の意味での人間の救済ということはありえない。それが突き当たっているのが今の時代の暴力性だろうと思っています。
なぜ人間の根源に暴力性があるのだろうか、という話になってゆくのですが、これは虐待というものを解き明かしていくときに必ず突き当たらなければならない。これは制度や人間のためにという言葉では解決のつかないもの。それは人間の精神世界のものです。そこへ突き当たっていくんだと思われます。
暴力はいくつかの形があります。それは暴力が成り立っていくのは密室化した中でです。つまり、そのとき「色んな人間がいていいんだよ」、「色んな価値観があるんだよ」。そういう世界が全部消されてしまって、「一つの価値観しかない」という閉鎖的な状況の中で暴力というものが行なわれてくる。というふうに言えると思います。
家庭内の暴力というのは、いつも「お前のため」「愛情」だとか「こうするのが良いことだ」ということで一つの方向に人間を縛り付けている。それを私たちは親の愛情だと思ってきました。また「家族」という言われかたでくくられてきました。ところが「家族」という言われ方の中に、よく見ていくと暴力による力の支配という形がよくあります。で、力による支配は、必ず力の強いものが弱いものを所有し支配するという構造をもちます。ですから親は子どもを支配し、子どもを所有する。「私の子ども」「私の妻」という形で、所有格で呼ぶんです。そういう呼び方がぴったりくるような所有の仕方をする、ってことがあります。
そうすると、そのときに「妻らしくする」「子どもらしくする」と言うのは、私の考える「子どもらしく」です。じゃあ、私の考えるということの根拠はどこにあるか、というと、それは社会一般で言われる子どものサンプル、それが私の身体を通って「私のもの」となってくる、という図式を常に取り続けるんだと思います。
家族間の関係というのは、密室化すればするほどそれはパワーゲームになります。ですから力の強いものが弱いものを支配する、という形になってきます。そういう形で小さい子に最も暴力が行きます。力の強いものから弱いものに暴力が流れるという図式は家族の年齢と体力の差によって逆転する、ということです。これは連鎖というものを解いていくときのひとつの見方かな、と思います。
| [2]に続く ≫≫ |