それに対して私は、一応、かなりの年数『平家物語』を読んでまいりました。その私が取り上げてみるのは――これは学会におきましても問題になっておりまして、特に歴史学者と、それから我々文学者の共通の課題になっているのですが、結論的に言いますと、『平家物語』がどのような歴史のとらえ方をしているか、どういう歴史の見方をするか、ということ。歴史の語り方。そんなことが今一番重要な課題になっています。
そういうことを直接皆様にお話したいと思います。
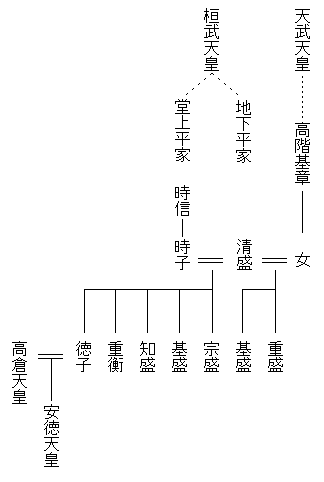
平成アーカイブス <研修会の記録>
以前 他サイトに掲載していた内容です
|
私は、教壇に立つようになりまして、かなりの年数が経ちます。その間、あちらこちらの公開講座に出させていただいておりますけれど、このようなお寺さんに招かれましたのは2度目です。1度目は兵庫県尼崎市の大覚寺で、琵琶の演奏会をかねて、平家琵琶の音楽の問題について、私のつたないお話したことがございます。それからお寺さんでは今日で2度目であります。おそらくこれが最後になるのではないかな、と思います。
先ほどここで讃歌をお唄いになった本多さんが、いま愛知淑徳大学の有能な事務職にいらっしゃるんですけど、その本多さんからお声がかかりまして、「ええ!」と思ったんですが、まさか、本願寺で話をする機会に恵まれるということは想像しなかったんです。
私、神戸生まれでございまして、両親とも亡くなっているのですが、お世話になったお寺は、いずれも神戸の本願寺のお西さんのお寺でございます。私の家の宗派が浄土真宗のお西です。講演のお話をいただいて、こういう場にお招きいただき、不思議なご縁だな、と思っています。
今日お話しいたします『平家物語』にある話というのは、私にとって非常に懐かしいテーマでありまして――ある雑誌に論文を書きました。そうすると、当時の早稲田大学教授だった福井康順さんという、大変立派な宗教学者ですけれど、その福井康順さんから手厳しい批判をいただきました。そういう問題をまたここでお話しするということは、本当に不思議だな、と思っております。
さっそく話に入ります。
先ほど、事務局の醍醐さんから、私のところへメモが回ってきまして、ある方から、「今日出席する予定だったが参加できない、ついては質問があります」ということですが、第一の質問が、「最近平家物語がブームになっているらしい。一体それはなぜなのか?」というご質問です。
確かに、例えばこの近くの丸善にまいりましても、文学のコーナーがありまして、「平家」と大きく書かれています。何だろうか? と思ったら、そこに女性作家の宮尾登美子さんの『平家物語』が積んであるわけですね。
さらに、ここに持ってまいりましたが、岩波文庫の『平家物語』ですね。私が一枚かんでいますが、私と仕事をした梶原正昭さんはもう亡くなりました。これを文庫本にしたのですが、ちょうどこの「岩波文庫」が一つの転機を迎えまして、文庫本の人気投票があったわけです。岩波文庫で1番関心の高いもの100点を選ぶ、ということをやったんですね。そうしますと、何と驚いたことに、『平家物語』が第50位でした。ということで、そんなに平家物語が読まれるのかなぁ、ということを、あらためて私自身も驚いたんです。
ただ、宮尾さんの『平家物語』の場合は、非常に現代的な関心をもって、人間関係の中で登場人物をとらえる、ということが大きな関心になっている。そういうことが現代人の我々の関心を呼ぶのですね。
それに対して私は、一応、かなりの年数『平家物語』を読んでまいりました。その私が取り上げてみるのは――これは学会におきましても問題になっておりまして、特に歴史学者と、それから我々文学者の共通の課題になっているのですが、結論的に言いますと、『平家物語』がどのような歴史のとらえ方をしているか、どういう歴史の見方をするか、ということ。歴史の語り方。そんなことが今一番重要な課題になっています。
そういうことを直接皆様にお話したいと思います。
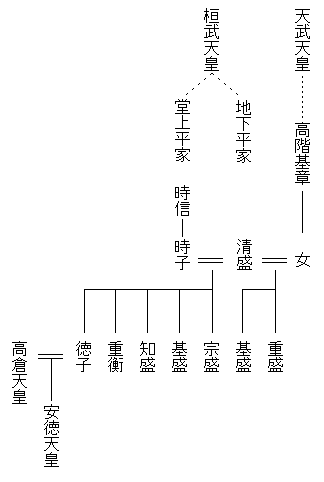
いきなり本論に入りますけれども、『平家物語』には色々な登場人物が出てまいります。その中で余り目におとめになることは無いだろうと思いますけれども、本日のプリントの裏側に平家の系図が書いてあります。その系統をご覧いただきますと、ここに2つの系統があって、
堂上平家というのは、京都にとどまりまして、そして京都王朝の中に生きて来た家系です。平時信、その子どもが平時子。それから平時忠がいます。その時子と、一方の地下平家、これは京都から外へ出まして、地方を回った家系です。特にその中の伊勢平氏です。忠盛やその息子の清盛が中核になります。
それから一方、関東に下っていった人たちもいる。これらの系統を地下平家といっています。その地下平家の平清盛と堂上平家の時子との間に、ご覧のように
それからもう一つ、天武天皇の系統を引いているところの
なお、清盛の義理の母親にあたります池の禅尼がいまして、その子に平頼盛がいまして、一口に平家と申しましても、大きく分けますと、伊勢平家の系統の中で、平時子の血筋をひく家系と、それから高階の娘の血筋をひく家系、もう一つ池の禅尼の家系、この3つの系統が非常に複雑な争いをやっていたわけです。
現代の作家は、こうした生き方を考えていくわけですけれども、私の場合は必ずしもそういうことに興味を持たない。むしろ今日取り上げますのは、清盛と時子との間に生まれました
プリントの最初のページに戻っていただきますと、作者が不明でありますけれど、お能の『重衡』という曲がございます。別名「
それに対して、もう10年前くらいになりますでしょうか、東京大学の教養学部の有能な能の研究者、松岡心平さんが中心になりまして、「橋の会」という能の若手の会―― 本日の催しも、浄土真宗の中で若い方がこういう場を企画して下さった訳ですけれど、能の世界におきましても、若手が色々実験をやってる訳です。その「橋の会」におきまして、数年前に、松岡さんが中心になってこの『重衡』を復曲したのです。一度松岡さんに名古屋に来ていただいて、名古屋でも話をしてもらったことがございました。

その『重衡』という曲を簡単に言いますと、最初のプリントを出して下さい、それを御覧いただきたいのですけど、左のほうに地図があります。
『重衡』という曲は、まずワキの旅の僧が京都から奈良へとやってきまして、そこで奈良の奈良坂あたりだと思いますが、一人の里の老人が疲れきって坂を登ってくるのに出会います。そういう光景が描かれているんです。
そして、一々読みませんけれど、そこへ出てきた老人が、奈良坂に到達いたしまして、地図には見えませんけれど木津、木津川という川があるんですね。その木津から坂道を登ってきて、そして奈良坂へと到着する。そして「やっと着いた」というセリフがあって、その老人が、そばにあった奈良坂の桜の木に近寄りまして、旅僧と話をします。そうしているうちに、何だか様子が変になってきまして、やがて問題の里の老人が、すうっと桜の木陰に隠れてしまう。実はこれは幽霊です。そして修羅能の場合はしばしばあるのですが、出てくる幽霊というのは後半の主人公の亡霊なんです。その化身なんです。これはだいたい修羅能の場合、定型になっています。
そしてこの旅僧に対してですね、問題の出てきた老人が実は重衡の化け物らしいということを、ちらちらと匂わせる。そしてすうっと隠れてしまう。
プリントの「構成」とあるところを見て下さい。
まず最初は、ワキの登場=京都から奈良への道行。そして、シテが登場する=人間のはかなさの
後半に入りますと、いよいよ重衡がそのまま出て来ます。修羅能の場合には、後から出てくるシテは、これは原則としてワキ僧にしか見えないことになっています。周りから見ても全然分らない。前半の場面で応答をしたワキにしか見えない、ということになっています。それを我々観客が見てる。これが修羅能というものであります。
重衡が、『平家物語』にも語っているところですけれど、大変な罪を犯したために、現在地獄に居て非常に苦しむ、ということを語って消えてしまう。
非常に暗い曲です。ですから、一般には愛好されなかったんだろうと思います。特に足利将軍などが嫌いました。江戸時代でも嫌われました。余りに暗いですから。
さて、このプリントの2枚目に系図を出しました。そこから話が始まります。ちょっと物語りの順番を狂わせていますが、当面私は、なぜ修羅能で重衡の亡霊が出てきたか、ということをお話いたします。
まず、出てきた場所が、特殊な空間・場所です。ただの場所ではありません。京都ではありません。木津川から奈良坂へさしかかった、そういうところへ現れた。一体それはなぜか。そして重衡は現在、地獄で獄卒に責められて大変苦しい思いをしている。なぜそうなったのか、ということです。
『平家物語』は全十二巻ありますけれど、重衡の物語は、第九巻に見られます。第九巻で、「一の谷合戦」が行われます。
私が『平家物語』に長くつきあうことになった。これはやはり私が神戸に生れた、そして地元がそういう平家物語の舞台であった、ということが私の生涯を決定したのですが、その一の谷の合戦で、大勢の平家の君達が討ち死にをする。その中でただ一人、生け捕りになるのが、平重衡です。
そこのところ、巻九「重衡生捕」を読んでみます。
【巻九 一の谷合戦 重衡生捕】
本三位 中将[ 重衡卿 は、[ 生田森 の[ 副 将軍にておはしけるが、[ 其勢 みな[ 落 ち[ 失 せて、[ 只 主従二騎にたり給ふ。三位中将、[ 其 日の装束には、かちにしろう黄なる[ 糸 をもッて、[ 岩 に[ 村千鳥 ぬうたる[ 直垂 に、紫すそごの鎧着て、[ 童子鹿毛 といふ、[ 聞 ゆる名馬に乗り給へり。めのと[ 子 の後藤兵衛[ 盛長 は、しげ目ゆ[ い の直垂に、火[ お どしの鎧[ 着 て、三位中将の[ 秘蔵 せられたりける[ 夜目 なし[ 月毛 に[ 乗 せられたり。梶原[ 源太景季 ・[ 庄 の四郎[ 高家 、大将軍と目をかけ、鞭、あぶみをあはせて[ 追 ッかけたてまつる。[ 汀 には、たすけ[ 舟 いくらもありけれども、うしろより敵は[ 追 ッかけたり。のがるべきひまもなかりければ、[ 湊河 ・かるも河をもうちわたり、[ 蓮 の池をば[ 馬手 に[ 見 て、[ 駒 の林を[ 弓手 になし、[ 板 やど・須磨をもうちすぎて、西をさいてぞ[ 落 たまふ。[ 究極 の名馬には[ 乗 りたまへり。[
ただ一人、ここで重衡は逃げる。この重衡が、結局「めのと子の後藤兵衛盛長」に見捨てられる。
武家社会において「めのと子」とは、同じ母親から乳をもらった子を「めのと子」といいますけれど、一人の乳母を仲介とした子どもどうしの関係というのは、非常に密接であります。そういう「めのと子」の盛長に見捨てられたのです。
そしてこの後、重衡は海に乗り入れて、逃げられるかと思ったが、生け捕りになってしまう。 梶原景季に追われて生け捕りにされてしまったわけです。やがてこの重衡たちが都に連行されます。巻十の『大路渡し』というところです。
ご参考までに申しますと、このテキストは、岩波の『新大系(新日本古典文学大系)』で、この『平家物語』の文庫本の前身です。今日は持ってきませんでしたけれど、『新大系』に拠っています。
今日持ってきたプリントは、元の『新大系』のテキストによっています。
一の谷の合戦で、重衡は生け捕りになってしまった。
【巻十 大路渡し 内裏女房】「同」は寿永3年、西暦1184年です。同 十[ 四 日[
同 十[ 四 日、いけどり[ 本三位 中将[ 重衡卿 、[
源氏物語と違って、読んでいて分かりますね。非常に短く、文章が分かりやすいでしょ。難しいところもありますけれど。それから、一つひとつの言葉がはっきりしています。こういうところに、『平家物語』が、もともとは琵琶法師によって語られた、ということがあるわけですね。
一方、これらが物語として語られた時、本当ならば文字を通して見るんじゃなくて、耳によって聞いて理解する。そういう文体であると思います。そういうことが、非常に『平家物語』を読みやすくさせているということでしょう。
<
いけどり本三位 中将[ 重衡卿 、六条を東へわたされけり。[
六条大路を東へ渡された。つまり、おそらく京都の羅城門あたりから北上して、それを六条大路を東に向かうわけです。
小八葉 の車に、[ 先後 の簾をあげ、左右の物見をひらく。[
これは完全に見せしめです。普通は閉じて乗る車ですけれど、それを全部開けてあるわけです。捕虜ですから見せしめです。
これは「ぜんご」です。「先後」と書いて「ぜんご」と読みます。土肥 次郎[ 実平 、[ 木蘭地 の[ 直垂 に[ 小具足 ばかりして、[ 随兵 卅余騎、車の先後[
車の先後にうちかこンで守護し奉る。京中の貴賎、是 を[ 見 て、「あないと[ を し、いかなる罪のむく[ ひ ぞや。いくらもまします[ 君達 のなかに、かくなり給ふ事よ。入道殿にも二位殿にも、おぼえの[ 御子 にてましまいしかば、[
注釈を入れますと、重衡がそういう辱めにあって、京都の大路を見せしめのためにさらし者になっているわけです。「京中の貴賎」がこれを見て、「あないとをし」と同情する。『平家物語』の場合、物語を展開しますのに、出てくる人物への思いというものを―― 例えば皆さんは、自分の思いを語るわけですけれど、語り物というのは、状況を見ている京都の人たちの思いを重ねてみているわけですね。こうしたところに、作家の見る『平家物語』とは違った、いわゆる琵琶法師の平家物語の特色があるのです。
京中の貴賎、是 を[ 見 て、「あないと[ を し、いかなる罪のむく[ ひ ぞや。いくらもまします[ 君達 のなかに、かくなり給ふ事よ。[
入道殿とは清盛です。清盛はこの前に亡くなっています。<二位殿>とは清盛の妻の時子ですね。<おぼえの御子>というのは、非常に大事にされた。かつこれは、系図を御覧になってわかりますように、末の子ですよね、おそらく、やはり末の子であることから、清盛と母親の二位殿の思いが深かった、ということでしょう。
御一家 の人々もおもき事に思い奉り給ひしぞかし。院へも内へも[ 参 り給ひし時は、[ 老 たるも[ 若 もところを[ お きてもてなし奉り給ひし物を。[
大変に評価している。なぜその重衡がこういうひどい目に遭うのか、というと、<
重衡は、六条を東に来て六条河原まで来ます。河原というのは、昔は刑場です。河原はご承知のように、昔は京都の町では不幸があった場合に、鳥部野へ持っていって葬られるということは非常に少ないわけです。ほとんど投げ捨て状態です。鴨川へ持っていって流しちゃうんです。こうしたことから刑場にもなったのですが、その河原まで渡されたのです。つまり刑場まで行って、また引き返すわけで、これはかなり厳しい刑科ですね。
そして
かへッて故中御門藤中納言家成 卿の八条堀河の[ 御 だうにすゑたてまッて、土肥次郎守護し奉る。[
そういう場面が描かれています。つまり、捕虜となって大路をさらし者になる過程で、京都の人たちの同情を買った。そして、その京都の人たちが「いやあ、こんなひどい目に遭うのも、<南都をほろぼし給へる、伽藍の罰にこそ>」と言っている訳です。
やがて重衡は京都でしばらく待機をします。その時に、重衡が親しくしていた女房、「内裏女房」と申しますけれど、一人女性がいた。その女性に手紙を送る。最後は女性と対面を許されることになるのですけれど、その重衡の手紙を、使者知時が持って女房をたずねます。
その時に、
此 人のこゑとおぼしくて[
出かけて行くと、女房らしい、その女房の声がして、
いくらもある人のなかに、三位中将しも先ほどの京都の人たちと全く同じ事を内裏女房は言うわけですね。生取 にせられて、[ 大路 をわたさるゝ事よ。人はみな奈良を焼たる罪のむく[ ひ と[ 言 ひあへり。[
<中将もさぞ
<わが心におこッては>・・・決して私は意識的には焼こうとはしなかった。
けれど、<
手々 に火をはなッて、おほくの[ 堂塔 を[ 焼 はらふ。[ 末 のつゆ、[ 本 のしづくとなるなれば、われ[ 一人 が罪にこそならんずらめ[
私は直接手を下していないけれど、結果責任を負う。その悪党たちとの攻めぎあいがあり、、その時に対決した結果火を放ったわけで、自分は直接火を放っていない。しかし結果的には、その罪は、大将としての自分のところへ来てしまう。つまり結果責任です。自分は、直接手を下していないけれども、結果責任を負うことになる。
と・・・つまり内裏女房はそういうことを言っているわけです。重衡がこういうことを言っていた、と同じことを言って同情するわけですね。言 ひしか。げにさとおぼゆる」とかきくどき、さめざめとぞなかれける[
ある事件があり、ある罪を犯した時に、その罪の責任を誰がとるか。つまり結果責任ということですけれども、これは例えば戦後派の作家、堀田善衛が『方丈記私記』を書いている。小説ではない、自分が『方丈記』読む場合には、こういう読み方をします、という『方丈記私記』。その『方丈記私記』の中で、東京大空襲について結果責任を言う。
実は今日話をしていますこの件について、現在の明治学院大学の国際学部の教授マイケル・ワトソンという人がいまして、オーストラリア人です。最近は国際化いたしまして、外国人が日本文学の古典を講義するという場面がしばしばあるわけです。数年前ですが、マイケル・ワトソンさんの平家物語の講義を聴講しました。最初から最後まで英語で済ます。その講義を聴いたときに、彼はこの重衡についてこう言ってるわけです。つまり「日本人の戦争に対する一つの責任の取り方がここにある」と、そういうことを言う。
次のプリントをご覧ください。
「南都炎上」とあります。どうして重衡は奈良の都を焼き払うことになったのか、ということです。さあ、ここが私の言いました「歴史の読み方」です。『平家物語』は平家物語なりの一つの歴史の読み方をしているわけです。それをとらえようという場合に、結局『平家物語』が一連の事件をどういう見解でもって語ってきたか、ということが解読のポイントになるわけです。
南都炎上に関しては、巻第四と巻第五、第四巻と第五巻が課題になります。この巻四というのは、後白河天皇に息子が何人かいるわけですが、その中でも特に劣り腹であったために日の目を見なかった、非常に不遇な皇子がいたんです。
この高倉宮以仁王に対して、当時、
この辺は巻第四の「源氏揃」「鼬之沙汰」「信連」「競」というところです。そして頼政たちが、作戦として自分たちでは手が出せないものですから、比叡山の延暦寺を味方につけようとします。そしてまず最初は彼らは三井寺に逃げ込む。そして三井寺から比叡山の延暦寺に協力を要請するわけです。
ところが延暦寺はそれを「No」と言います。拒否するわけです。しょうがないので、結局三井寺から以仁たちは奈良・南都の興福寺・東大寺に協力を要請します。幸いにして興福寺・東大寺の人たちはOKする。そのために三井寺に居ては危ないというので、三井寺から宇治を通って奈良へ下っていく途中、討ち死にをしてしまいます。その後、平家は、以仁王の反乱に協力をした三井寺をまず焼き討ちする。これが「三井寺炎上」です。その時の総大将が平重衡です。大変な罪を犯すわけです。
そして巻五に入ります。京都にいると、色々と、特に延暦寺の連中がうるさく、奈良の寺も色々騒ぎを起こすものですから、平家が京都を見捨てるのです。逃げ出して神戸の福原に都移しをやります。
そうしているうちに、やがて源頼朝が兵を上げるというのが「早馬」です。「早馬」「朝敵揃」、物語が進んでまいりまして、やがて「富士川」の合戦へと進むわけです。
当時平家は、福原の京、神戸に居ましたが、色々と公卿仲間でも不満が出てくる。さらに、何かと寺院社会から節介を受けるので、「これは困った」というんで、都を京都に戻す。戻しておいた上で、「あの憎きやろう、結局こうなったのも」と、最初三井寺を焼き討ちしていますけれども、さらに、「自分たちの手を煩わせた南都を焼き討ちにかけようというのが次の「奈良炎上」ですね。
【巻五 奈良炎上】
都には又、「高倉宮、園城寺 へ[ 入御 時、南都の[ 大衆 同心して、あまッさへ御[ 迎 へに[ 参 る条、これもッて[ 朝敵 なり。されば南都をも三井寺をも[ 攻 めらるべし」といふ程こそありけれ、[ 奈良 の大衆おびたゝしく[ 蜂起 す。[
平家がそういう動きを示しますと、いち早く奈良の興福寺・東大寺の在職たちが動き出す。
そこでの摂政殿、藤原基通が、
「存知の何か考えている事があるなら筋を通せ、ということを言う。旨 あらば、いくたびも[ 奏聞 にこそ及ばめ」[
つまり大衆たちは納得しないんです。それで動くわけです。仰下 されけれども、一切もちゐたてまつらず。[
使者が来ますと、その使者に対して狼藉をはたらきます。右官 の[ 別当忠成 を御使にくだされたりければ、「しや[ 乗 物よりとッてひきおとせ。もとゞりきれ」[
忠成色をうしなッてにげのぼる。つぎに右衛門佐つまり人形を作って、清盛を侮辱します。親雅 をくださる。これをも、「もとゞりきれ」と大衆ひしめきければ、とる物もとりあへずにげのぼる。其時は[ 勧学 院の[ 雑色 二人がもとゞりきられにけり。又南都には大なる[ 球丁 の玉を[ 作 ッて、これは平相国のかうべ[
つまり安徳天皇のおじいさんですね。詞 のもらしやすきは、わざはひをまねく[ 媒 なり、詞のつゝしまざるは、やぶれをとる道なり」と[ 言 へり。この入道相国と申すは、かけまくもかたじけなく、[ 当今 の[ 外祖 [
天魔の所為、それにしてこういう乱暴なことをさせるんだろう、と。当今 の[ 外祖 にておはします。それをかやうに申ける南都の大衆、[ 凡 は[ 天魔 の所為とぞ[ 見 えたりける。[
入道相国かやうの事どもつたへ瀬尾太郎兼康を南都地方の警察長官にしておいたわけですね。聞き 給ひて、いかでかよしと[ 思 はるべき。かつがつ南都の[ 狼藉 をしづめんとて、備中国住人[ 瀬尾 太郎[ 兼康 、大和国の[ 検非所 に[ 補 せらる。[
何をやっても、お前達絶対に手を出してはいかんぞ、と。清盛は、あらかじめ言いふくめておく。兼康 五百余騎で南都へ[ 発向 す。「[ 相構 て[ 衆徒 は[ 狼藉 をいたすとも、[ 汝等 はいたすべからず。[
物の具なせそ。弓矢は持っていっちゃいけない。<とて>・・・つまり全く丸腰でもって派遣するわけです。弓箭 な[ 帯 しそ[
とて向 けられたりけるに、大衆かゝる内儀をば[ 知 らず、[ 兼康 が[ 余勢 六十余人からめとッて、一々にみな[ 頸 をきッて、[ 猿沢 のはたにぞ[ 懸 け[ 並 べたる。入道相国大にいかッて、「さらば[
この辺のところ、非常に上手いですね。じっとこらえている。堪えにこらえてる。最後のところで、清盛はついに堪忍袋の緒を切るわけですね。
入道相国大にいかッて、「さらば南都をつまりみな徒歩の兵です。馬に乗っていません。攻 めよや」とて、大将軍には[ 頭 中将[ 重衡 、[ 副 将軍には中宮[ 亮道盛 、都合其勢四万余騎で、南都へ[ 発向 す。大衆も老少きらはず、七千余人、[ 甲 の[ 緒 をしめ、[ 奈良坂 ・[ 般若寺 二ケ所[ 路 をほりきッて[ 堀 ほり、かいだてかき、さかも[ 木 ひいて[ 待 かけたり。平家は四万余騎を[ 二手 にわかッて奈良坂・般若寺二ケ所の[ 城■ に[ を しよせて、[ 時 をどッ[ と つくる。大衆はみなかち[ 立 [
ちょっと飛ばします。官軍 は馬にてかけまはしかけまはし、あそここゝにおッかけおッかけ、さしつめひきつめさんざんに[ 射 ければ、ふせくところの大衆、かずをつく[ ゐ て[ 討 たれにけり。[
夜 いくさになッて、くらさはくらし、大将軍[ 頭 中将、[ 般若寺 の門の前にうッ[ 立 ッて、「火を[ 出 せ」との給ふ程こそありけれ、平家の勢のなかに、[ 播磨 国住人、[ 福井庄下司 、二郎大夫[ 友方 といふもの、たてをわり、たい松にして、[ 在家 に火をぞかけたりける。十二月廿八日の夜なりければ、風ははげしゝ、ほもとは[ 一 つなりけれども、[ 吹 まよふ風に、おほくの[ 伽藍 に[ 吹 かけたり。[ 恥 をも[ 思 ひ、名をも[ お しむほどのものは、奈良坂にて[ 討死 し、[ 般若寺 にして[ 討 たれにけり。[ 行歩 にかなへる物は、吉野・[ 十津河 の方へ[ 落 ゆく。あゆみもえぬ老僧や、[ 尋常 なる[ 修学者 、[ 児 ども、[ 女 [ 童部 は、大仏殿の二階のうへ、[ 山階 寺のうちへわれさきにとぞにげゆきける。大仏殿の二階の上には、千余人のぼりあがり、かたきのつゞくをのぼせじと、[ 橋 をばひいてンげり。[ 猛火 はまさしう[ を しかけたり。おめきさけぶ声、[ 焦熱 ・大焦熱・[ 無間阿■ のほの[ を の[ 底 の[ 罪 人も、これには[ 過 ぎじとぞ見えし。[
ということで、大変なことになってしまうわけです。そしてその挙句に興福寺・東大寺の伽藍をいっせいに焼き払ってしまう。大変なことになってしまった。
さあ、これで皆さんもお分かりですね。平家の側から考えてみれば、清盛は清盛なりの理由があった。これはどちらが悪いか分りませんよね。重衡が大将軍に指名されて、ちょっとした小競り合いがきっかけで、夜いくさになって、暗いですから「火をつけろ」と言った。そしてさらに南都の大衆たちが騒ぐものですから、どんどんと事がエスカレートして、結果的にこういう大変な阿鼻叫喚の結果を招いてしまったわけです。
そのことで、先に申しましたように、重衡が一の谷で生け捕りになって、そしてそれが京都に連行された時に、まず京都の人たちが、「いや、よりによって重衡がねー、あの清盛と母親の二位殿に大変可愛がられていた末っ子の重衡が、大将軍になって、そして目の前にこうして一人生け捕りになって、大路をさらし者になって、非常に可哀相だな」と言った。
そして内裏女房であった女房も同じ事を言って、重衡自身が「結果的に自分が南都炎上の責任を負わざるを得なくなるであろう」と言った、ということを彼女自身が聞いているんですね。そのことを重衡の恋人である内裏女房がつぶやいているわけです。
こういう軍記物語、私は「いくさ物語」という言い方をしますが、「いくさ物語」には、しばしばこういう女性が登場します。その女性が主人公である武将たちの生き方・死に方にからまってくるわけです。平家物語でも数人の女性が出てきます。太平記の場合も大勢の女性が出てきます。
特にその中で、重衡に関しましては、まずここで内裏女房という女性が出てくる。もう一人、実は彼の本妻は
それからもう一人、この大納言佐と重衡との間には、子どもが無かった。そのことを最後、「よくぞ子どもが無かった。なまじっか子どもがあったら、もっと辛い目に遭った、自分が殺された。処刑されてた」と言っている。
もう一人女性がいまして、重衡には子どもが無いとなっていたけれども、一人男の子がいたんですね。そしてその男の子を産んだ母親がいます。その男の子が逃げ回っている時に捕まっちゃうわけです。捕まって、そしてその子どもが、平家の生き残りであるという理由で、首をはねられてしまいます。その子どもの首を、許しを請うてもらい受けまして、その首を身体につけて離さないで、あちこち巡礼しまして、最後に天王寺に行きます。
天王寺へ行ってみると、髑髏御前と呼ばれます。身体からしゃれこうべを放さない。それが腐敗して臭ってくるわけですね。周りは皆嫌がって逃げ回るわけです。それを髑髏御前といって、その髑髏御前が結局天王寺から舟に乗って身投げをして死んでしまう。そういう物語が出てきます。その父親が重衡であった、という物語がくっついてくるわけです。
都合3人の女性が重衡に登場する。『平家物語』で重衡というのは、余り注目されないんじゃないかと思いますけれども、修羅能の『重衡』を見た場合に、この重衡が浮かび上がってくるわけです。その重衡の亡霊が出て来る、それも大変な罪を犯した場所であるわけで、そこへ出てくるのです。
木津川とは処刑された場所です。
ちょっとここで予定の40分になりましたので、10分間休憩を入れまして、今日の本編へ進みたいと思います。
〔next〕≫≫
【巻九 一の谷合戦 重衡生捕】
本三位 中将[ 重衡卿 は、[ 生田森 の[ 副 将軍にておはしけるが、[ 其勢 みな[ 落 ち[ 失 せて、[ 只 主従二騎にたり給ふ。三位中将、[ 其 日の装束には、かちにしろう黄なる[ 糸 をもッて、[ 岩 に[ 村千鳥 ぬうたる[ 直垂 に、紫すそごの鎧着て、[ 童子鹿毛 といふ、[ 聞 ゆる名馬に乗り給へり。めのと[ 子 の後藤兵衛[ 盛長 は、しげ目ゆ[ い の直垂に、火[ お どしの鎧[ 着 て、三位中将の[ 秘蔵 せられたりける[ 夜目 なし[ 月毛 に[ 乗 せられたり。梶原[ 源太景季 ・[ 庄 の四郎[ 高家 、大将軍と目をかけ、鞭、あぶみをあはせて[ 追 ッかけたてまつる。[ 汀 には、たすけ[ 舟 いくらもありけれども、うしろより敵は[ 追 ッかけたり。のがるべきひまもなかりければ、[ 湊河 ・かるも河をもうちわたり、[ 蓮 の池をば[ 馬手 に[ 見 て、[ 駒 の林を[ 弓手 になし、[ 板 やど・須磨をもうちすぎて、西をさいてぞ[ 落 たまふ。[ 究極 の名馬には[ 乗 りたまへり。[ 【巻十 大路渡し 内裏女房】
同 十[ 四 日、いけどり[ 本三位 中将[ 重衡卿 、六条を東へわたされけり。[ 小八葉 の車に、[ 先後 の簾をあげ、左右の物見をひらく。[ 土肥 次郎[ 実平 、[ 木蘭地 の[ 直垂 に[ 小具足 ばかりして、[ 随兵 卅余騎、車の先後にうちかこンで守護し奉る。京中の貴賎、[ 是 を[ 見 て、「あないと[ を し、いかなる罪のむく[ ひ ぞや。いくらもまします[ 君達 のなかに、かくなり給ふ事よ。入道殿にも二位殿にも、おぼえの[ 御子 にてましまいしかば、[ 御一家 の人々もおもき事に思い奉り給ひしぞかし。院へも内へも[ 参 り給ひし時は、[ 老 たるも[ 若 もところを[ お きてもてなし奉り給ひし物を。[ 是 は南都をほろぼし給へる、[ 伽藍 の[ 罰 にこそ」と[ 申 あへり。河原までわたされて、かへッて[ 故中御門藤中納言家成 卿の八条堀河の[ 御 だうにすゑたてまッて、土肥次郎守護し奉る。[
<中略>
知時もッて内裏へ参 りたりけれ[ 共 、ひるは[ 人目 のしげゝれば、[ 其 へんちかき[ 小屋 に[ 立 ち[ 入 ッて、日を[ 待暮 し、[ 局 の[ 下口 へんにたゝずンで[ 聞 けば、[ 此 人のこゑとおぼしくて、「いくらもある人のなかに、三位中将しも[ 生取 にせられて、[ 大路 をわたさるゝ事よ。人はみな奈良を焼たる罪のむく[ ひ と[ 言 ひあへり。中将もさぞ[ 言 ひし。「わが心におこッてはやかねども、[ 悪党 おほかりしかば、[ 手々 に火をはなッて、おほくの[ 堂塔 を[ 焼 はらふ。[ 末 のつゆ、[ 本 のしづくとなるなれば、われ[ 一人 が罪にこそならんずらめ」と[ 言 ひしか。げにさとおぼゆる」とかきくどき、さめざめとぞなかれける。[ 【巻五 奈良炎上】
都には又、「高倉宮、園城寺 へ[ 入御 時、南都の[ 大衆 同心して、あまッさへ御[ 迎 へに[ 参 る条、これもッて[ 朝敵 なり。されば南都をも三井寺をも[ 攻 めらるべし」といふ程こそありけれ、[ 奈良 の大衆おびたゝしく[ 蜂起 す。摂政殿より、「存知の[ 旨 あらば、いくたびも[ 奏聞 にこそ及ばめ」と[ 仰下 されけれども、一切もちゐたてまつらず。[ 右官 の[ 別当忠成 を御使にくだされたりければ、「しや[ 乗 物よりとッてひきおとせ。もとゞりきれ」と[ 騒動 する間、忠成色をうしなッてにげのぼる。つぎに右衛門佐[ 親雅 をくださる。これをも、「もとゞりきれ」と大衆ひしめきければ、とる物もとりあへずにげのぼる。其時は[ 勧学 院の[ 雑色 二人がもとゞりきられにけり。又南都には大なる[ 球丁 の玉を[ 作 ッて、これは平相国のかうべとなづけて、「うて」「[ 踏 め」なンぞと申ける。「[ 詞 のもらしやすきは、わざはひをまねく[ 媒 なり、詞のつゝしまざるは、やぶれをとる道なり」と[ 言 へり。この入道相国と申すは、かけまくもかたじけなく、[ 当今 の[ 外祖 にておはします。それをかやうに申ける南都の大衆、[ 凡 は[ 天魔 の所為とぞ[ 見 えたりける。[
入道相国かやうの事どもつたへ聞き 給ひて、いかでかよしと[ 思 はるべき。かつがつ南都の[ 狼藉 をしづめんとて、備中国住人[ 瀬尾 太郎[ 兼康 、大和国の[ 検非所 に[ 補 せらる。[ 兼康 五百余騎で南都へ[ 発向 す。「[ 相構 て[ 衆徒 は[ 狼藉 をいたすとも、[ 汝等 はいたすべからず。物の具なせそ。[ 弓箭 な[ 帯 しそ」とて[ 向 けられたりけるに、大衆かゝる内儀をば[ 知 らず、[ 兼康 が[ 余勢 六十余人からめとッて、一々にみな[ 頸 をきッて、[ 猿沢 のはたにぞ[ 懸 け[ 並 べたる。入道相国大にいかッて、「さらば南都を[ 攻 めよや」とて、大将軍には[ 頭 中将[ 重衡 、[ 副 将軍には中宮[ 亮道盛 、都合其勢四万余騎で、南都へ[ 発向 す。大衆も老少きらはず、七千余人、[ 甲 の[ 緒 をしめ、[ 奈良坂 ・[ 般若寺 二ケ所[ 路 をほりきッて[ 堀 ほり、かいだてかき、さかも[ 木 ひいて[ 待 かけたり。平家は四万余騎を[ 二手 にわかッて奈良坂・般若寺二ケ所の[ 城■ (←土篇に郭)に[ を しよせて、[ 時 をどッ[ と つくる。大衆はみなかち[ 立 うち物[ 也 。[ 官軍 は馬にてかけまはしかけまはし、あそここゝにおッかけおッかけ、さしつめひきつめさんざんに[ 射 ければ、ふせくところの大衆、かずをつく[ ゐ て[ 討 たれにけり。[ 卯刻 に[ 矢合 して、一日[ 戦 ひ[ 暮 らす。夜に入ッて、奈良坂・[ 般若寺 二ケ所の[ 城■ ともにやぶれぬ。[ 落 ちゆく衆徒のなかに、[ 坂 四郎[ 永覚 といふ[ 悪僧 あり。打物[ 持 ッても弓矢をとッても、力のつよさも、七大寺・十五大寺にすぐれたり。もえぎ[ 威 の[ 腹巻 のうへに、[ 黒糸威 の[ 鎧 を[ 重 ねてぞ[ 着 たりける。[ 帽子甲 に五牧甲の緒をしめて、[ 左右 の手には、[ 茅 の[ 葉 のやうにそッたる[ 白柄 の[ 大長刀 、[ 黒漆 の大太刀[ 持 つまゝに、[ 同宿 十余人、前後に[ 立 て、[ て ンがいの門よりうッて[ 出 でたり。これぞしばらくさゝへたる。おほくの[ 官兵 、馬の足[ 薙 がれて[ 討 たれにけり。されども官軍は大勢にていれかへいれかへ[ 攻 めければ、[ 永覚 が前後・左右にふせくところの同宿みな[ 討 たれね。永覚たゞひとりたけゝれど、うしろあらはになりければ、南をさいて[ 落 ちぞゆく。[
夜 いくさになッて、くらさはくらし、大将軍[ 頭 中将、[ 般若寺 の門の前にうッ[ 立 ッて、「火を[ 出 せ」との給ふ程こそありけれ、平家の勢のなかに、[ 播磨 国住人、[ 福井庄下司 、二郎大夫[ 友方 といふもの、たてをわり、たい松にして、[ 在家 に火をぞかけたりける。十二月廿八日の夜なりければ、風ははげしゝ、ほもとは[ 一 つなりけれども、[ 吹 まよふ風に、おほくの[ 伽藍 に[ 吹 かけたり。[ 恥 をも[ 思 ひ、名をも[ お しむほどのものは、奈良坂にて[ 討死 し、[ 般若寺 にして[ 討 たれにけり。[ 行歩 にかなへる物は、吉野・[ 十津河 の方へ[ 落 ゆく。あゆみもえぬ老僧や、[ 尋常 なる[ 修学者 、[ 児 ども、[ 女 [ 童部 は、大仏殿の二階のうへ、[ 山階 寺のうちへわれさきにとぞにげゆきける。大仏殿の二階の上には、千余人のぼりあがり、かたきのつゞくをのぼせじと、[ 橋 をばひいてンげり。[ 猛火 はまさしう[ を しかけたり。おめきさけぶ声、[ 焦熱 ・大焦熱・[ 無間阿■ のほの[ を の[ 底 の[ 罪 人も、これには[ 過 ぎじとぞ見えし。[
〔next〕≫≫