平成アーカイブス <研修会の記録>
以前 他サイトに掲載していた内容です
|
7月11日勉強会1 [講師:西光義敞先生]
今年の勉強会は私が3回お話させていただきますので、今日はテーマの確認をしながら話を深めていきたいと思います。私が一方的に話をするより、無駄なようですけど、そういうことをしていった方が、よりよい勉強会になると思います。
自己紹介になりますが、奈良県の山奥の寺で、檀家が40件、過疎化が進んでこのごろは30何軒になりましたけど、そこの小寺の住職でございます。これでは到底やっていけませんので、大学を終えるなり、教師と僧侶の二束のわらじを履いてきた身でございます。初めは17年間平安学園、後は龍谷大学で勤めさせていただきました。
どういうことをやってきたのかと申しますと、大学では仏教学をやったんですけど、平安学園時代にカウンセリングということを知り、そちらが非常に大事だということが分かりましたので、その研究をやっているうちに、「真宗カウンセリング研究会」というのを立ち上げて、それを中心に教育というものを考え、それがご縁で龍谷大学では社会学の社会福祉の教師として定年を迎えさせていただきました。
人は、「西光、お前何やってるんだ」とよく言われるんですけど、結局、一つは真宗信者というものが中心にあります。カウンセリングというのがもう一つ中心にあります。具体的には、社会福祉のことをやってきました。だいたいこの3つの領域から、今日皆さんが問題にしようとされている「家族・家庭」ということを取り上げる、と申しますのは、家族家庭というのでは、余りにもテーマが大きすぎます。
ですから、なぜ皆さんがこのテーマを選んで勉強なさりたいのか、分からないことには話があちらにいったり、こちらにいったりしてしまいます。そうかといって私が勝手に問題を絞り込んでしまいますと、「そういう話を聞きたいと思って来たんではない」となってしまいます。そういうところをきっちりして、勉強会でも研修会でもご法座でも進めていくことが私は大事だと思います。
そういう意味で、今日のところは、初めに20分間問題提起みたいな話をさせてもらって、後は皆さんのご意見を聞きながら、まとめさせていただきますが、そういう会の進め方自体が勉強会だと思って下さい。
皆さんはKJ法というのはご存知でしょうか。ちょっとこれ、注目してもらっていいんじゃないかと思います。資料提供はいくらでも致します。何かことを始めるには、できるだけ多方面から色々な声を上げてもらう。加えていくのです。それが大事。初めからぱっと問題を決めてしまうとまずい。参加してる人全員が知恵をとことん出し合って、だから非常に雑多なものが出て来ます。そうすると大概「時間が無いから」とか「収拾つかなくなるから」と抑えていくでしょう。それはまずいと。できるだけ沢山出る方がいい。
それをどうまとめるか、まとめ方の方法が「KJ法」なんです。これは川喜田二郎という人の頭文字をとっているんですね。雑多な意見をまとめて、どう整理して、皆の共通意識とするか。余り出すぎると収拾がつかないけれども、それをまとめるのは、グループに組み立てて整理し、重要でないのは後回しにするか、捨てていって、優先順序をつけていかねばなりませんね。そして問題をすっきりさせて次の段階に移っていくという、そういう方式でやってみたらいいんじゃないでしょうか。
私が問題提起でどんどん課題を出していきますから、次の話し合いの刺激材料になればいいと思っています。
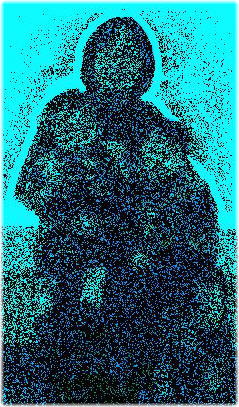
「家族・家庭」といいますと、学問としては社会学になります。「家族社会学」というのは混迷を極めているんです。 前近代、封建時代は複合家族だった。一軒の中に爺ちゃん婆ちゃんお父ちゃんお母ちゃんもいる。孫がいる。そして兄弟がたくさん居て、一つの家の中に同居していた。それぞれが場を与えられている。 ただ、女性の地位にしましても、面白いですね。良い時代は「娘」と言うんです。「良い女」と書きます。家に入っていくと「嫁」になる。家族制度の中で位置みたいなものが固定してまして、一応共通にわきまえて、分を守っておれば、それなりに安定した生活ができた。これが前近代です。
ところが、明治以降、日本が近代化して、西洋に追いつけ追い越せ、さらに戦後はそういう傾向が急ピッチで進みまして、「家族制度そのものが封建的だ」ということで、法制的にはもう無いですね。だから、遺産相続でも、長男に全部ごっそり譲るということは無くなってきまして、皆に均等に分けるようになりました。前近代とは違った法律で動いています。けれども現実には、遺産相座億でも、地域や人によってやり方が違います。きっちり分けているところもあれば、皆が醜い争いをする、という話があります。皆さんの近辺では、どうでしょうか。またそれは皆さんの問題になっているでしょうか。
戦後のモデルは、日本は「複合家族的なものは古い。早く脱ぎ捨てなくてはいけない」と、そういう意識できた訳です。モデルは西洋的、特に戦後はアメリカの家族家庭というものをモデルにして、ひとつの理想としては、「核家族化」ということが言われました。「複合家族」から「核家族」へというのが、戦後のひとつの夢だったわけです。
今までは親子中心に家を考えてきた。それも長男から長男へと遺産を受け渡していく。次男三男四男坊や女の人たちは、しばらく親元にいるけれど、皆親を離れていくという制度だったわけですね。それは制度としてはなくなった訳です。けれども長い伝統がありますから、制度がなくなっても、そういうやり方とか、前近代的意識をずーっと引きずりながら来ているんですね。
私たち共通の問題というのは、仏教・真宗が中心ですから、考えてみましても、独立して家を出て行って自由に好きな人と結婚して、新住宅に次男坊が住んでいるとしますね。仏壇つくらんでしょう。「何で?」と聞いたら、「まだ誰も死んでないから。仏壇は長男が守っているから、まつっているから」と言う。 仏壇というのはそういうものだと思われてしまっている。私たちにはそういう具体的な課題が突きつけられている。
「出た娘や息子には必ず新住宅に仏壇を買って与えます」と、そして「お勤めもきっちりしつけてきました」という家庭もあれば、無頓着な家庭もある。ひどい所では、「仏壇を作ると死を連想して余りいい気持ちがしない。死人もないのにどうして作らんならんのだ」と言う家庭もあります。真宗の家庭の中ですら意識のばらつきがある。皆さんは若いけれども、どういう家庭に住んでおられて、どういう家族関係で、例えば仏壇があったり、お参りをするという生活の仕方や考え方はどうなっているんでしょうか。 あるいは皆さんがお寺さんでしたら、檀家さんにどのように教化なさっているんでしょうか。これは非常に具体的な問題だと思いますね。
近代の理想のモデルは、親子中心ではなく夫婦中心の家庭になってきた。だからいつまでも親と同居するのは嫌だと、ひと時「家つき、カーつき、ばば抜き」という言葉があった。やっぱり住宅は建ててほしいんでしょうね。自動車も欲しい。だけども「ばば抜き」ですから、姑が居ては困る。夫婦で気楽に生きたい。
近年は夫婦中心、子どもは二人の四人家族が一つの典型的なモデルになってます。だからそういうことをイメージしながら考えてきたし、家族社会学としても、そこらへんを目指してやってきたんですが、これがどんどん壊れてきています。それが問題で、核家族がずっと維持できていればまだ日本は健全であると思いますが、その核家族が維持できなくなっているんです。
どういう意味かというと、まず女性というのは、昔は男が仕事をして稼いできて、家のやりくりは全部嫁がやるんだと。そういう時期があるものですから、しばらく女性が学校出てから働いても、「どうせ女やから」と、いつまでも雇う意識が、特に大きな企業になればなるほど無いんです。女にお茶くみやらせるとか、そこで男女差別の問題が大きくなってきた訳です。
教育レベルがどんどん上がってきまして、私も何十年と大学の教師してますけれど、どこの大学でも女子学生の方が多いんじゃないですか。それに真面目でよく勉強するのは男子より女子学生です。だから少なくとも対等か、それ以上になってきたわけです。それが就職になると、「なんで女性が差別されなならんねん」という意識が起こってくるのは当然ですから、男性と女性の問題をめぐってジェンダーの問題、セックスの問題が絡んできます。
家を中心に考えますと、昔は家の中に色んな機能があった。経済的機能、教育的機能、子育て機能、親を介護する機能、全部あって、それを一手に担っているのが女性です。特に年寄りの面倒みるとか、病気になったら介抱する、子どもを育てる、というのは女の仕事、嫁の仕事や、ということになっていたわけです。今でもそういう意識を引きずっている人はかなりあるんじゃないでしょうか。
ところが、それが動かなくなった。今から30年前でしたら、「ポストの数ほど保育所を造れ」という運動があった。新興住宅地で女性も働きに出ますから、赤ちゃんが産まれても、これを育てる者が家に居らんわけです。これを社会福祉では「保育に欠ける子」といいます。養護できない子は「養護に欠ける子」と、児童福祉法ではそう規定しています。そういう時に、養護に欠ける子のために施設として養護施設とゆうのができた。保育に欠ける子には保育所ができたわけです。
一定の地域の中で保育に欠ける子が産まれたら――父親は勿論働きに出ている、しかも戦後の企業は人使いが荒いから、夜通しで働いて、残業で遅く帰ってくる。だから家のことは何も知らんとおるんです。まして子どもを育てるということは何も知らない。で、逃げ口上は「もう寝させてくれよ。子育てはお前に任してあるから」と言って子育てから逃げようとしますね。そうすると、子育ての悩みはお母ちゃん1人なんです。
ところが女性も働きに出るということになりますので、保育に欠ける子がどんどん出てくる。これは誰の責任か、というと、「これは当然お母ちゃん、女の責任や」というふうに古い意識では当然視していたわけですけど、現代の社会福祉法では、保育に欠ける子を法的責任において保育しなければならないのは地方公共団体、具体的には福祉事務所なんです。 だからその頃は、保育に欠ける子をお母さんが連れて出て、福祉事務所の前に子どもをほっておいて、「保育に欠ける子は福祉事務所の責任でしょ」と言うて帰る事件がありました。 だからそのことをめぐっても、「無責任な母親が出た」と女性を非難する声、あるいは「福祉・保育所をもっと建てないからこういうことが起こる」と言うて保育所をもっと建てるように言ったり、大論争になったことがあります。
ところが今、「ポストの数ほど保育所を」という声はぴたりとやみました。どんどん村を離れ、伝統的な家を離れ、新興住宅地へ。大きく言えば、農山村から都市へ都市へと若い労働力が移動していきますから、農山村は急速に過疎化して、都市部は急速に過密化していきます。だから、過疎地は過疎地の家族問題が出てきた。過密地は昔なかったような家族問題が出てきた。次から次へと、今までの常識では理解できない問題が出てきて、それが極限状況にきて混乱している、というのが現在なんです。
社会福祉の領域で大きくいうと、皆家を持って住んでる。家は地域にあるわけでしょう。人間が住むというのは、どこかの地域に住む。天人ではないです、浮いている訳ではありません。その中に家があって、その中に人間が住んでいるわけです。そういう構造になってますね。 地域ぐるみで福祉を考えていこうというのが地域福祉です。個人個人に問題が出てきた場合には、やっぱりきめ細かくというんで児童福祉、老人福祉。障害者福祉、と細分化されてきた。法律もきめ細かくできたわけです。
ところが、地域福祉があって、生活保護法とか立派な法律がちゃんとできていても、家族福祉法が無いんです。社会福祉の領域でみても、家族・家庭というのは行政的にも福祉の観点からも見落としている。これが大きな問題なんです。
大きな社会福祉の流れは、どう動いているかというと、憲法の25条に基いて「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」。これは国民の生存権、福祉権を保証した、とっても大事な憲法なんです。社会福祉の勉強をする者、社会保障の問題を勉強をする者は、必ずここからスタートします。 そしてその次の第2項には「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と、これは国や地方公共団体の義務なんです。 先ほどの子育てをめぐって福祉事務所とお母ちゃんが押し付けをしている、というのはここからきてる訳です。 この憲法25条の精神に基けば、保育に欠けるというのは、、健康で文化的な生活ではないでしょう。ほっとかれる子どもも困るし、お母ちゃんは働けないでいる。だからそれを法的責任で面倒見るというのは、これを厚生大臣に任せるわけにはいかないからね、一番地域に密着した社会福祉行政の最前線の福祉事務所が責任を持たなくてはならない、ということになるわけですね。
そんな訳で、戦後日本の国は、健康で文化的な生活をするために社会福祉に随分力を入れて福祉六法というこんな厚い本ができる位に法律制度は充実してきたんです。それが大体昭和30年代に一応完成した。
ところが、その前提になっているのは「人生50年」という考え方なんです。そういうことをベースにしてすべて法律制度を作ってきた。ちょうど法律が出来上がった昭和30年代から40年代にかけて、急速に日本人の平均寿命が伸び、55歳、60歳、70歳になる。ふっと気が付いてみたら昭和40年代から50年代にかけては、世界トップの高齢化社会になってしまったんです。 長らくずっと、女性は平均寿命は84〜5歳、男性でも75〜6歳です。これは世界中で比較してもずっとトップなんですね。
歴史的に見ても、こういう高齢化社会は日本人の先祖は経験したことがない。だから横に各国と比較してみても、縦に先祖の歴史をたどっても、こういうふうに長生きできる時代というのは無かったわけですから、いまだ経験したことがない社会を生きているということ、これが基本ですね。
そこに問題があるのは、例えば、ヨーロパの国でしたら、人生50年から人生80年時代になるまでには、早いところで40〜50年、ゆったりしたところでは120年かかって徐々にそういう社会になっていく。ゆっくり転換してきているんです。その間に法律制度を作ってきたんです。 日本はわずか25年という短い時間に、あっという間に急カーブで上がっていますので、戸惑いが多いわけだから、法律制度がついていけない、国もどうしていいか分からない。各個人、各家でも、どうしていいか分からない、という不安が日常生活近辺で溢れているんですね。そのへんを考えて皆さんはこのテーマを取り上げてなさるのかな、と思うんですが、そのへんの問題意識はどうでしょうか。
ひとことでまとめるには「少子高齢化社会」です。平均寿命が84〜85歳に延びたということは、年寄りが長生きするということもありますが、昔は沢山子どもを産むけど大人になる前に死んでいった、乳幼児の死亡率が高かったけど、今は死なないですよ。医療が進んだおかげで。だからできるだけ子どもを少なく産んで、子育ても面倒だから、そして大事に育てようと、いうふうに全体の意識が変ってきた。特に女性は、自分が子どもを宿し出産するので、子沢山というのは嫌なんです。だからどんどん出生率が減ってきて、核家族の時には二人の親から二人の子どもができる。そうすると人口が安定して続くはずでしょ。それからまたどんどん出生率が減って、私が龍谷大学の福祉の専門の時代は1.5くらいになりました。これでは人口が減ってしまうから、若い人が多くの年寄りを支えんならん時代がやってくる、と。これは危機やから、もっと子どもを産む政策を考えなければいけないと、言うてたけど、止まらなかった。ところが今は1.3です。
だから、二人の親から、平均1.3やから、二人産む家もあるけれども、一人で結構やという若い人たちが増えてきたというわけです。 東京都に至っては1.0なんです。もう一人産んだらけっこう。平均でですよ。しかもこれはとどまらないだろう、という訳ですから、これは家族にとっても、国にとっても深刻な問題です。
そういう色々な問題があるわけですが、さて皆さんはこのテーマで3回にわたって何を勉強したいと思っているのか、皆さん一人一人の問題意識はどこにあるのか、話し合いをしていただきたいと思います。
| ≪≪ [back] | [next] ≫≫ |