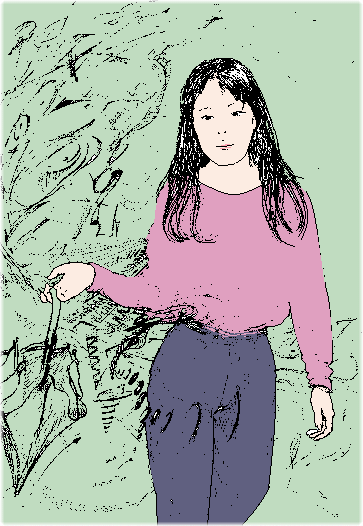
平成アーカイブス <旧コラムや本・映画の感想など>
以前 他サイトに掲載していた内容です
|
平成19年4月7日
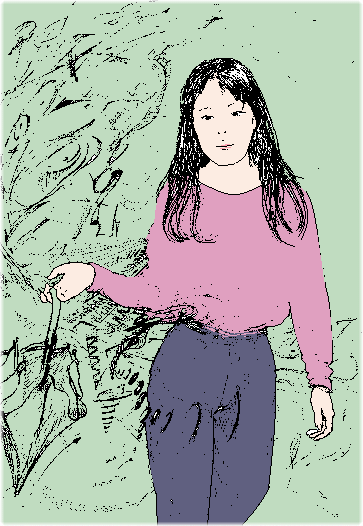
今年になって『千の風になって』という歌が話題になっている。特に詩。原文は英語だが、新井満らの翻訳で日本人にも馴染みとなり、特に昨年(平成18年)のNHK紅白歌合戦で歌われ全国に感動が行き渡った。
この詩は亡き人との関係を歌ったもので、〝I am not there〟<そこに私はいません>、〝a thousand winds〟<千の風になって>いると、壮大なスケールを奏でている。これはある意味、墓の存在意義を否定する内容とも聞こえるが、顧みてみれば古より〝人は死して星になる〟という表現もあるので同様の心情だろうか。とにかく人生を問う歌だけに一仏教徒の私としても大いに関心がある。これをどう解釈したら良いのか……もちろん、詩を解釈するのは野暮だと解ってはいるが、それでも私なりに留意点が見つかったので少し語らせてもらいたい。
ネットやCDなどで調べて解ったことだが、この詩にはほぼ二種の原文(英文)があるようだ。新井満さんが翻訳し秋川雅史さんによってNHK紅白歌合戦で歌われた詩の原文は以下の通りである。
a thousand winds
Author UnknownDo not stand at my grave and weep;
I am not there, I do not sleep.I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn's rain.When you awaken in the morning's hush,
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.Do not stand at my grave and cry;
I am not there, I did not die.
上記の翻訳文は日本語での歌詞が普及しているのでここには掲載しないが、詩の作者は不明となっている。しかし以下に掲載する同様の詩は、作者がメアリー・フライ(アメリカ人女性)となっている。母の墓前に参れない友人を勇気づけるために書かれた詩、ということだ。
Do not stand at my greave and weepどちらがオリジナルかは知らないし、感覚的なところに多少の差はあるが、ほぼ同様の意図で書かれた詩だろう。そこで私なりに後者の詩の意訳を試みてみた。
Words by Mary FryeDo not stand at my grave and weep
I am not there, I do not sleep
I am in a thousand winds that blow
I am the softly falling snow
I am the gentle showers of rain
I am the fields of ripening grain
I am in the morning hush
I am in the graceful rush
Of beautiful birds in circling flight
I am the starshine of the night
I am in the flowers that bloom
I am in a quiet room
I am in the birds that sing
I am in the each lovely thing
Do not stand at my grave and cry
I am not there I do not die
私のお墓の前で 涙しないで
そこに私はいません 終わりにしないで
私は千の風となって あなたに語りかけます
ふんわり降る雪となって あなたを包みます
しとしと注ぐ雨となり
野をうるおす穂となって
朝の静けさの中
美しい鳥の群れ飛ぶ中
優雅な舞いとともに 私はいるの
星のまたたきとともに 私はいるの
ほら花たちも咲き誇っているじゃない
静かな部屋だって素敵じゃない
鳥のさえずり一声ひと声が 私の歌よ
愛しさの一つひとつが 私の全てよ
私のお墓の前で 泣いたりしないで
そこに私はいません 終わりにしないで
直訳は他人に任せ、ここでは自分の感受性と求道心に任せてみた。そのため少し意訳が過ぎたかも知れないし、英文の韻をふむ形式は完全には再現できなかった(他の日本語訳では韻はほとんど無視されている)が、意図は汲み取ったつもりである。それは以下に示そう。
新井満さんは<I am in a thousand winds that blow>を<千の風になって あの大きな空を 吹きわたっています>と翻訳している。歌としてはその方がダイナミックだし、曲との関係もしっくりゆくのだろう。しかし、空を吹きわたっているだけでは亡き人が千の風になった意味はない。これでは単なる一服の清涼剤に過ぎないだろう。しかも下手をすると<民衆の阿片>と
肝心なのは、亡き人が今の私に突き当たってくることなのだ。千の風となり、雪となり、雨となり、愛しいもの一切となって私に突き当たってくることが尊いのである。ここに亡き人たちとの新たな関係を結ぶ要めがある。私が<千の風となってあなたに語りかけます>と意訳したのは、こうした本意があるからだ。
若山牧水に次のような歌がある。
垣根の外の水の音 耳には慣れて忘れはするが
忘れた音の聞こえるように 昔の母が憶われる
これは、亡き母の思い出が、大切な「忘れた音」を思い出させてくれるということで、仏教で言えば〝亡き人がご縁となり、浄土の呼びかけ(回向)を思い出させてくれる〟と味わうことができる。普段あまりに耳慣れて忘れていた大切な生命のつながり、血となり汗となり涙と報いた浄土の音が、亡き人の思い出とともに蘇り、私に突き当たって心身に響くのである。
また島田幸昭師は次のような名言を残してみえる。
大身を現して虚空に満ち 小身を現わして性根と成る
「大身」とは、尊いものが全体に映じられた姿で、「虚空に満ち」るとは、そのはたらきに障りがないことを言う。風に吹かれれば風に、星を見たら星のまたたきに、雨や雪にも四六時中、何か大切なものをそこに見出すのだ。これは一般的に言う「信仰」のことで、〝大いなるものに包まれている私〟、〝もったいなくも生かされている私〟という心情になっている。すると、風が私に語りかけ、雨が語りかけ、辺り一面が教えを説く先生となる。
私ごとで言えば、確か10歳の頃だと思うが、若狭の海に海水浴に行った帰り、振り返って見た山々から、尊くも無言の説法を聞く体験をした。当時の私は、これは〝個人的な体験〟だと思っていたが、後に経典を学んで〝普遍的な体験〟と知ることとなる。
また次に舎利弗、かの国にはつねに種種奇妙なる雑色の鳥あり。白鵠・孔雀・鸚鵡・舎利・迦陵頻伽・共命の鳥なり。このもろもろの鳥、昼夜六時に和雅の音を出す。その音、五根・五力・七菩提分・八聖道分、かくのごときらの法を演暢す。その土の衆生、この音を聞きをはりて、みなことごとく仏を念じ、法を念じ、僧を念ず。『仏説阿弥陀経』3 正宗分 依正段 より
鳥だけではない。木々が語りかけてくる、水が法を説く、大地が輝く、人々が輝く、全てが厳かな輝きをもって私に物事の本質を語るのだ。こうした信仰体験はあらゆる宗教に見出されるもので、まずは宗教の第一歩と言えよう。
しかし大抵の宗教はここで留まってしまっている。〝見えたものが尊い〟、これは大切な経験だ。しかしさらに大切なのは、見えたものではなく、見た自分の眼そのものの正体である。感じた自分そのものの歴史性である。仏教では、対象として見えたものは〝化身〟であると言う。先の『仏説阿弥陀経』では<このもろもろの鳥は、みなこれ阿弥陀仏、法音を宣流せしめんと欲して、変化してなしたまふところなり>と説く。では歴史性のある本体はどこにあるのか。それは「小身」に現われる。
「小身」とは、尊いものが私の身に満ちた姿で、自分の心身そのものである。
空が尊いのではない、太陽が尊いのではない。尊いのは「天上天下唯我独尊」と開かれたこの〝唯一無二の命〟であり、「自灯明・法灯明」と展開する自分の人生である。
これは<偉大なる天体よ! もしあなたの光を浴びる者たちがいなかったら、あなたははたして幸福といえるだろうか!>と叫んだツァトゥストラの序説とも通じるが(参照:{本地垂迹説について})、真に尊いものは、天体や自然から直接もたらされるものではなく、具体的な生命の辛苦を経てこの身に報いた性根にある。この性根のことを仏教では<如来回向の真実信心>とも<本願他力>とも言う。
五濁悪世の衆生の 選択本願信ずれば
不可称不可説不可思議の 功徳は行者の身にみてり『高僧和讃』118 結讃
風が語りかける、鳥が語りかける、山が語りかける、全てのものが語りかける、と思っていたのは実は仮の姿(化身)。本当は、私に成り切った性根(報身)が叫ぶのである。風が私にぶち当たり、鳥の姿が私にぶち当たり、山が私にぶち当たり、経験する全てのものが私にぶち当たり、私の性根が叫ぶのである。
師は、<山ではなく私が大鐘であり、山が撞木となって私を突く。すると私が響いて、私の中から新たな価値が生み出されてくる>と仰られた。大身と小身で言えば、大身に包まれて小身が溶けてしまうのが信仰、小身が大身を飲み込むのが信心である。こうして先の「信仰」は「信心」に、そして「信楽」へと脱皮してゆく。
先の私ごとで言えば、以前から生死の問題で深く悩んでいたことが縁となり、山が私にぶち当たり私が感動する。この感動がきっかけとなって、私は芸術の道を志すようになった。あの感動が、山だけではなく、海や川や人々を見る眼を純化させたのである。
そう、今までは立場が逆だったのだ。親鸞聖人はじめ真実信心を得られた方はこの逆転を直し、信心正因を明らかにされた。すると〝大いなるものに生かされている〟と仰ぐ信仰が正され、〝信心によって全てを生かす〟と、主体が立ち上がる宗教が生まれた。これこそが人間を生かし切る
ただし、短絡的に「私は性根を獲得した」「私は信心を得た」と言うと、これは嘘である。〝性根が生まれたためにかえって性根無しの自分の姿が見えた〟ということが本当である。〝いつか性根を得よう〟と欲する本当の欲が生まれたことを〝性根が生まれた〟〝信心を得た〟というのである。だから自分で「私は真実の信心者だ」と言うのは間違い。これは傲慢な法執に陥った邪定聚に過ぎない。あくまで<後に生れんひとは前を訪へ>(安楽集)というように、先人たちを尊敬し、周囲の人たちから道を聞かせてもらう態度が真実信心者のあかしだ。自分を「真実信心者」と誇って凝り固まる者に法が浸みてゆく道理はない。
相手を尊べばみな仏。仏々相念の念仏。亡き人を尊べは、亡き人は姿を現して風や星となり、化身となって虚空に満ちるが、本体はこの身に至りて性根と成り、新たな道程を生み出す基礎力となるのである。
当ホームページはリンクフリーであり、他サイトや論文等で引用・利用されることは一向に差し支えありませんが、当方からの転載であることは明記して下さい。
なおこのページの内容は、以前 [YBA_Tokai](※現在は閉鎖)に掲載していた文章を、自坊の当サイトにアップし直したものです。